Image may be NSFW.
Clik here to view.
「日本家屋構造」の紹介、小屋組の項を続けます。今回が小屋組の紹介の最後になります。
はじめは第四十一図。
Image may be NSFW.
Clik here to view.
標題が「八 與次郎組、渡腮及ワナギ枘」とあり、そのはじめが「第一 與次郎組仝ワナギ枘」となっています。
仝という字は同の古語で「同じ」という意です。
しかし、與次郎組仝ワナギ枘が何を言っているのか、よく分りません。と言うのも、上の図、すなわち甲と、下の図乙・丙・丁とは関係がないからです。つまり、與次郎組が必ず乙〜丁の仕口をともなうわけではありません。
そこで、以下では、それぞれを分けて紹介、説明することにします。
「第四十一図甲は、與次郎組と呼ばれる小屋組のつくり方を示した図。
この小屋組は、梁間:梁行の長さが大きいとき、中柱あるいは土蔵のように梁上に束柱を建て、その束柱に、左右から小屋梁を登り木として枘差しとする方法。枘は、図のように束柱に対して段違いに差し、図の左側の登り木のように込み栓か、右側のように鼻栓を打つ。
その際、登り木の下端を束柱に5分、上端を束面にそろうように斜めに胴付を設ける。」
註 與(与)次郎 弥次郎兵衛(やじろべえ)の別称
弥次郎兵衛 (「広辞苑」による)
玩具の一。短い立棒に湾曲した細長い横棒を付け、その両端に重しを取付けたもの。
指先などで立棒を支えると、釣合いをとって倒れない。與(与)次郎人形。釣合人形。正直正兵衛。
與次郎組 説明のために下図をつくりました。
Image may be NSFW.
Clik here to view.
図の赤色部分を天秤梁と呼び、濃い黄色部分を與次郎束、黄色部分が登り木。
黄色の部分が弥次郎兵衛に似ていることから弥次郎兵衛組、與次郎組と呼ばれるようになったようです。
與次郎束を受ける天秤梁上の桁行の横材を、
中引梁(なかびきばり)、地棟(ぢむね)、牛曳(うしびき)、牛梁(うしばり)などと呼びます。
「日本家屋構造」では中引梁と呼んでいるようです。
ただし、この横材を、かならずこのような形、天秤梁で受けなければならないわけではありません。
両側の妻面の棟通りに柱を建て、その間に太い横材を架け、その上に與次郎組を組む方法あります。
妻面の梁上の束柱に架ける場合もあります。
つまり、上図の黄色部分の「原理」が重要で、その「応用」は任意で、定型があるわけではありません。
また、この横材に対する呼称が日本語では多数存在します(そういう例は、他にもあります)。
おそらく、西欧語では、一つのものに対して、このように多様な名は示されず、
普通は、そのものを示すのに相応しい代表的名称を紹介し、その他をいわば「方言」として紹介するでしょう。
「方言」とは、同一物に対しての、地域や人による呼び方の「違い」。
日本でも、この多様な名称は、「方言」のはずです。
その方言が「中央」に集められ「均質に」紹介されると、そのすべてを「知る」ことが意義あることだ、
と思う方が生まれます。
なかには、それならば、一つの呼称に「統一」しよう、と思われる方も居られるでしょう。
私は、それは、どちらも無意味なことだ、と考えます。
私は、そのすべてを知る必要はない、と思っています。私たちは辞書である必要はない、と思うからです。
知らなければならないのは、そういう策を採る理由:謂れです。
それが分ればそれでいい、と私は思います。
いろんな呼び方を知っていることは、博識ではない、のです。
ましてや、一つの呼称に統一しよう、などというのはもってのほか。
「標準語」という言い方は、今は死語になりつつあり、あらためて「方言」の意味が見直されています。
かつての「標準語」は、「共通語」という呼び方になっています。
このように、いろいろな呼び方がある場合、当方の「意図」を示すために私が採る手段は、
その部分を「絵に描いて示す」ことです。
天秤 (「広辞苑」による)
?質量を測定する器械。
(棒の)両端に皿をつるし、一方に測ろうとする物を、他方に分銅をのせて、水平にし、質量を知る。
?天秤棒(両端に荷をかけ中央を肩に当ててになう棒)の略。
第四十一図の説明の続き。
「図の乙は、柱に腕木を取付ける渡腮(わたりあご)の仕口と、柱径より小さい棟木を柱に取付ける仕口:ワナギ枘を示した図。
ワナギ枘は、柱枘の左右を棟木の大きさに彫り取り棟木を嵌め込み、枘に割楔を打つ。
図の丙は、棟木の木口の図で、点線は、中の2本が枘を示し、外側の線は柱の左右を棟木に嵌め込む部分を示している。嵌め込む深さは2分程度。」
註 説明文だけでは分り難いので、絵にしてみました。
Image may be NSFW.
Clik here to view.
原文の示しているのは、左側の図のような納め方と思われます。
中の図のように、柱頭を低い位置で止めるのが普通かもしれません。
その方が、「柱が上の材を受けている」感じが強いからです。その事例が右の写真。
「・・・腕木は、柱に渡り欠きをつくり差し通す。
渡り欠きは、腕木を図の乙の点線のように欠き取り、同じく柱には点線のように孔を穿つ。
柱に穿つ孔は、腕木外寸より高さを5分程度大きく、孔の下端は、柱の面より5分ほど入った位置から中を5分上がった位置で刻む。
腕木の欠き取り寸法は、長さは柱径より1寸程度小さく、深さは5分程度。
腕木を柱の孔の上端にそって差し込み、所定の位置で渡り欠きを噛ませる。孔の上端にできる空隙に、両端から楔を打ち締めると腕木は固定される。
腕木の先端上端に小根枘をつくり、桁を差し、割楔を打って締める。」
註 ここに示されている図は、普通、簡素な門などで使われる方法で、與次郎組とは無関係です。
参考として、「日本建築辞彙」から、腕木を用いた門、腕木門:木戸門の図を転載します。
Image may be NSFW.
Clik here to view.
第四十一図では、桁を腕木の先端にそろえていますが、この図のようにするのが一般的です。
続いて節をあらため、「蔀を柱に差す仕口」
普通、蔀とは、下註で触れるように、板戸のことを言います。それゆえ、その理解の下では、この標題が何を言っているのかよく分りません。
そこで、そのあたりについて、下註で、前もって説明しておくことにします。
註 蔀(しとみ) 「日本建築辞彙」(新訂版)の解説
・・・蔀は日除(ひよけ)の戸なり。また風雨を除ける物なり。
その上方に蝶番(ちょうつがい)などを設け、開きて水平となし、多端を吊るようになしあるものを、
吊蔀(つりしとみ)または揚蔀(あげしとみ)という。・・・
蔀 「字通」の解説
声符は部。日光や風雨をさえぎる戸板、しとみ、小さい蓆(むしろ)をいう。
[名義抄]シトミ・カクフ(囲う)・オホフ(覆う)
釣る蔀戸の詳細は、江戸時代初頭の光浄院客殿の開口部をご覧ください。
江戸っ子は、ヒとシを混同し、蔀をヒトミと発音する人が多く居ました。
商家では、店の通り側全面を、昼間は開け夜は閉じます。閉じる手段は開口部を板戸で塞ぐことでした。
この板戸を、蔀あるいは蔀戸と呼びました。古来の由緒ある語です。
閉じ方にはいろいろあります。雨戸もその一です。しかし、雨戸には戸袋(とぶくろ)がいります。
そして、戸袋を設けると、開口がその分狭くなる。
そこで編み出されたのが、板戸を開口の上部に擦り揚げる方法です。
普通、揚戸(あげど)あるいは摺り揚戸(すりあげど)などと呼びます。
この板戸は普通の雨戸を横にした形(たとえば縦2尺8寸×横5尺7寸)をしています。
開口高さが1間程度のときは、この板戸を2枚仕込みます。
この揚戸(摺り揚戸)を、古来の呼び名を使い蔀戸と呼んだのです。
ところが江戸っ子はシトミドをヒトミドと呼び、その音に字を与え人見戸(ひとみど)という表記まで生まれます。
「日本家屋構造」の著者は、漢字は蔀戸と記し、音ではヒトミドと表記しているのです。
以下に、一般的な商家の店先の正面図を「日本建築辞彙」から転載します。簡素な例です。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![]()
図の人見梁とは蔀梁のこと。同じく人見柱は蔀柱。
蔀梁は、この梁の上部の内側に蔀戸を仕舞いこむための呼称。
古の蔀戸は、この横材に金物で吊ってありました。今なら蝶番。それゆえ蔀釣梁。
蔀柱は、蔀梁が取付く柱の意。
人見には、人に見せる、人に見られる、という意が込められていたようです。
店の間口が広いときは1枚の戸では納まりません。たとえば、上図の柱間が2間のとき、
戸締りの際には中間(図の黄色に塗った束柱の下になります)に取り外し可能な柱を1本立て、
その左右にそれぞれ1枚の戸を仕込みます。
この柱の呼称は閂(かんぬき)、黄色に塗った束柱の呼称は箱束(はこづか)でした。
閂は、開き戸を閉じたとき、外から開けられないように、内側に通す横材を言います。
そして、この横材を保持するコの字型の金物が閂金物、閂持金物(かんぬきもちかなもの)。
閂と同じような役割を持つため、この取外し可能な柱を閂と呼んだようです。
以上の下準備をした上で、本文の解説に入ります。
「第一 蔀造りの仕方
第四十二図は、多くの商家の表入口上に設けられる蔀:蔀梁の構造を示す。蔀梁の上部の小壁部分は、蔀戸をしまうための戸袋となる。
蔀梁の取付けは差鴨居と同じだが、その裏面(店の内側)に板戸1枚を納められるほどの深さの决り欠き(しゃくり かき)をつくる。
夜間、店を閉じているとき、開口部を、上下2枚の板戸:蔀戸で閉じる。
開店時には、先の蔀梁の欠き込み部:戸袋に、上段の蔀戸を突き上げて納め、下段の蔀戸は、仕舞った上段の蔀戸の位置まで押上げ、ツマミを差し、止め置く(2枚の戸が並んで納まっている)。
この戸袋部を左右に仕切る束柱を箱束と呼び、蔀戸を滑らす溝が彫られている。
開口を閉じるとき、この箱束の下に、箱束と同じ断面の柱を立てる。この取外し自由な柱を閂と呼ぶ。
蔀梁は柱の外面から飛び出して取付くため、柱への枘を2枚に分け(二枚枘)、枘の先端を少し薄くして柱に差し、込み栓を打つ。このような先を薄くした枘をこき枘と呼ぶ。」
註 蔀梁の仕口を二枚枘とし、さらに先端を薄く斜めに殺ぐのは、枘孔の位置が柱の外面に近いため、
通常の枘で差すと、柱に亀裂が生じるおそれがあり、それを避けるための工夫と考えられます。
枘を上下2枚に分けるのも同じ理由だと思われます。
最後は出桁造り(だしげた づくり)の解説ですが、この紹介のために、揚戸を設けた商家の店先の断面図を載せます。
左側は「日本家屋構造」製図編にある出桁造りの商家の矩計図、右は近江八幡にある旧・西川家の矩計図(「重要文化財 旧西川家住宅修理工事報告書」より)。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![]()
先の第四十二図は、左側の商家についての解説と見なしてよいと思われます(ただ、この図では、箱束が壁で隠れています)。
右の西川家の例は、柱間が1間、ゆえに板戸は1列、2枚の例で、閂、箱束はありません。なお、西川家では、蔀戸ではなく摺り揚戸(すりあげ ど)と呼んでいます。蔀戸は、江戸の呼び方だったのかもしれません。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![]()
最後は、出桁造について。
この解説は上の矩計図を参照しつつお読みください。
「第二 出桁造り
第四十三図は、出桁造りの説明図。出桁造りは蔀造りの階上の造りに多く見られる。
図の甲は、肘木を取付けるための肘木受。肘木受は、肘木よりも高さは1寸5分以上大きく、厚さは2寸くらいとする。
註 肘木=腕木
図の乙は、柱間の中間で肘木受に取付く肘木の仕口。大きさは幅は柱と同寸、高さは柱径より3分ほど大きくする。仕口は大入れ蟻掛け。大入れは3〜4分。
柱に取付く肘木は、長枘を設け、柱に差し、先端は間柱まで伸ばし釘打ちとする。
図の丙は、出桁の姿図。出桁の大きさは、幅:柱の8/10×高さ:幅+3分。肘木に渡り欠きで架ける。
出桁の内側には、肘木の上端位置に小穴(こあな)を突き、図のように天井板を納める。
註 小穴 細い幅の溝。この場合は、板の厚さ分の幅、深さは板厚以上。溝を彫ることを突くという。
出格子(で ごうし)の出は、普通6寸以上8寸以下。柱は3寸角内外、上は肘木に枘差し・込み栓打ち、下端は頚切りをして瓦を嵌め込む。格子台の下端は瓦上端に置く。」
小屋組については、これで終りです。
次は縁側のつくりかたになります。
Clik here to view.
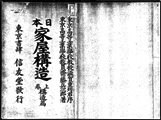
「日本家屋構造」の紹介、小屋組の項を続けます。今回が小屋組の紹介の最後になります。
はじめは第四十一図。
Image may be NSFW.
Clik here to view.

標題が「八 與次郎組、渡腮及ワナギ枘」とあり、そのはじめが「第一 與次郎組仝ワナギ枘」となっています。
仝という字は同の古語で「同じ」という意です。
しかし、與次郎組仝ワナギ枘が何を言っているのか、よく分りません。と言うのも、上の図、すなわち甲と、下の図乙・丙・丁とは関係がないからです。つまり、與次郎組が必ず乙〜丁の仕口をともなうわけではありません。
そこで、以下では、それぞれを分けて紹介、説明することにします。
「第四十一図甲は、與次郎組と呼ばれる小屋組のつくり方を示した図。
この小屋組は、梁間:梁行の長さが大きいとき、中柱あるいは土蔵のように梁上に束柱を建て、その束柱に、左右から小屋梁を登り木として枘差しとする方法。枘は、図のように束柱に対して段違いに差し、図の左側の登り木のように込み栓か、右側のように鼻栓を打つ。
その際、登り木の下端を束柱に5分、上端を束面にそろうように斜めに胴付を設ける。」
註 與(与)次郎 弥次郎兵衛(やじろべえ)の別称
弥次郎兵衛 (「広辞苑」による)
玩具の一。短い立棒に湾曲した細長い横棒を付け、その両端に重しを取付けたもの。
指先などで立棒を支えると、釣合いをとって倒れない。與(与)次郎人形。釣合人形。正直正兵衛。
與次郎組 説明のために下図をつくりました。
Image may be NSFW.
Clik here to view.

図の赤色部分を天秤梁と呼び、濃い黄色部分を與次郎束、黄色部分が登り木。
黄色の部分が弥次郎兵衛に似ていることから弥次郎兵衛組、與次郎組と呼ばれるようになったようです。
與次郎束を受ける天秤梁上の桁行の横材を、
中引梁(なかびきばり)、地棟(ぢむね)、牛曳(うしびき)、牛梁(うしばり)などと呼びます。
「日本家屋構造」では中引梁と呼んでいるようです。
ただし、この横材を、かならずこのような形、天秤梁で受けなければならないわけではありません。
両側の妻面の棟通りに柱を建て、その間に太い横材を架け、その上に與次郎組を組む方法あります。
妻面の梁上の束柱に架ける場合もあります。
つまり、上図の黄色部分の「原理」が重要で、その「応用」は任意で、定型があるわけではありません。
また、この横材に対する呼称が日本語では多数存在します(そういう例は、他にもあります)。
おそらく、西欧語では、一つのものに対して、このように多様な名は示されず、
普通は、そのものを示すのに相応しい代表的名称を紹介し、その他をいわば「方言」として紹介するでしょう。
「方言」とは、同一物に対しての、地域や人による呼び方の「違い」。
日本でも、この多様な名称は、「方言」のはずです。
その方言が「中央」に集められ「均質に」紹介されると、そのすべてを「知る」ことが意義あることだ、
と思う方が生まれます。
なかには、それならば、一つの呼称に「統一」しよう、と思われる方も居られるでしょう。
私は、それは、どちらも無意味なことだ、と考えます。
私は、そのすべてを知る必要はない、と思っています。私たちは辞書である必要はない、と思うからです。
知らなければならないのは、そういう策を採る理由:謂れです。
それが分ればそれでいい、と私は思います。
いろんな呼び方を知っていることは、博識ではない、のです。
ましてや、一つの呼称に統一しよう、などというのはもってのほか。
「標準語」という言い方は、今は死語になりつつあり、あらためて「方言」の意味が見直されています。
かつての「標準語」は、「共通語」という呼び方になっています。
このように、いろいろな呼び方がある場合、当方の「意図」を示すために私が採る手段は、
その部分を「絵に描いて示す」ことです。
天秤 (「広辞苑」による)
?質量を測定する器械。
(棒の)両端に皿をつるし、一方に測ろうとする物を、他方に分銅をのせて、水平にし、質量を知る。
?天秤棒(両端に荷をかけ中央を肩に当ててになう棒)の略。
第四十一図の説明の続き。
「図の乙は、柱に腕木を取付ける渡腮(わたりあご)の仕口と、柱径より小さい棟木を柱に取付ける仕口:ワナギ枘を示した図。
ワナギ枘は、柱枘の左右を棟木の大きさに彫り取り棟木を嵌め込み、枘に割楔を打つ。
図の丙は、棟木の木口の図で、点線は、中の2本が枘を示し、外側の線は柱の左右を棟木に嵌め込む部分を示している。嵌め込む深さは2分程度。」
註 説明文だけでは分り難いので、絵にしてみました。
Image may be NSFW.
Clik here to view.

原文の示しているのは、左側の図のような納め方と思われます。
中の図のように、柱頭を低い位置で止めるのが普通かもしれません。
その方が、「柱が上の材を受けている」感じが強いからです。その事例が右の写真。
「・・・腕木は、柱に渡り欠きをつくり差し通す。
渡り欠きは、腕木を図の乙の点線のように欠き取り、同じく柱には点線のように孔を穿つ。
柱に穿つ孔は、腕木外寸より高さを5分程度大きく、孔の下端は、柱の面より5分ほど入った位置から中を5分上がった位置で刻む。
腕木の欠き取り寸法は、長さは柱径より1寸程度小さく、深さは5分程度。
腕木を柱の孔の上端にそって差し込み、所定の位置で渡り欠きを噛ませる。孔の上端にできる空隙に、両端から楔を打ち締めると腕木は固定される。
腕木の先端上端に小根枘をつくり、桁を差し、割楔を打って締める。」
註 ここに示されている図は、普通、簡素な門などで使われる方法で、與次郎組とは無関係です。
参考として、「日本建築辞彙」から、腕木を用いた門、腕木門:木戸門の図を転載します。
Image may be NSFW.
Clik here to view.

第四十一図では、桁を腕木の先端にそろえていますが、この図のようにするのが一般的です。
続いて節をあらため、「蔀を柱に差す仕口」
普通、蔀とは、下註で触れるように、板戸のことを言います。それゆえ、その理解の下では、この標題が何を言っているのかよく分りません。
そこで、そのあたりについて、下註で、前もって説明しておくことにします。
註 蔀(しとみ) 「日本建築辞彙」(新訂版)の解説
・・・蔀は日除(ひよけ)の戸なり。また風雨を除ける物なり。
その上方に蝶番(ちょうつがい)などを設け、開きて水平となし、多端を吊るようになしあるものを、
吊蔀(つりしとみ)または揚蔀(あげしとみ)という。・・・
蔀 「字通」の解説
声符は部。日光や風雨をさえぎる戸板、しとみ、小さい蓆(むしろ)をいう。
[名義抄]シトミ・カクフ(囲う)・オホフ(覆う)
釣る蔀戸の詳細は、江戸時代初頭の光浄院客殿の開口部をご覧ください。
江戸っ子は、ヒとシを混同し、蔀をヒトミと発音する人が多く居ました。
商家では、店の通り側全面を、昼間は開け夜は閉じます。閉じる手段は開口部を板戸で塞ぐことでした。
この板戸を、蔀あるいは蔀戸と呼びました。古来の由緒ある語です。
閉じ方にはいろいろあります。雨戸もその一です。しかし、雨戸には戸袋(とぶくろ)がいります。
そして、戸袋を設けると、開口がその分狭くなる。
そこで編み出されたのが、板戸を開口の上部に擦り揚げる方法です。
普通、揚戸(あげど)あるいは摺り揚戸(すりあげど)などと呼びます。
この板戸は普通の雨戸を横にした形(たとえば縦2尺8寸×横5尺7寸)をしています。
開口高さが1間程度のときは、この板戸を2枚仕込みます。
この揚戸(摺り揚戸)を、古来の呼び名を使い蔀戸と呼んだのです。
ところが江戸っ子はシトミドをヒトミドと呼び、その音に字を与え人見戸(ひとみど)という表記まで生まれます。
「日本家屋構造」の著者は、漢字は蔀戸と記し、音ではヒトミドと表記しているのです。
以下に、一般的な商家の店先の正面図を「日本建築辞彙」から転載します。簡素な例です。
Image may be NSFW.
Clik here to view.

図の人見梁とは蔀梁のこと。同じく人見柱は蔀柱。
蔀梁は、この梁の上部の内側に蔀戸を仕舞いこむための呼称。
古の蔀戸は、この横材に金物で吊ってありました。今なら蝶番。それゆえ蔀釣梁。
蔀柱は、蔀梁が取付く柱の意。
人見には、人に見せる、人に見られる、という意が込められていたようです。
店の間口が広いときは1枚の戸では納まりません。たとえば、上図の柱間が2間のとき、
戸締りの際には中間(図の黄色に塗った束柱の下になります)に取り外し可能な柱を1本立て、
その左右にそれぞれ1枚の戸を仕込みます。
この柱の呼称は閂(かんぬき)、黄色に塗った束柱の呼称は箱束(はこづか)でした。
閂は、開き戸を閉じたとき、外から開けられないように、内側に通す横材を言います。
そして、この横材を保持するコの字型の金物が閂金物、閂持金物(かんぬきもちかなもの)。
閂と同じような役割を持つため、この取外し可能な柱を閂と呼んだようです。
以上の下準備をした上で、本文の解説に入ります。
「第一 蔀造りの仕方
第四十二図は、多くの商家の表入口上に設けられる蔀:蔀梁の構造を示す。蔀梁の上部の小壁部分は、蔀戸をしまうための戸袋となる。
蔀梁の取付けは差鴨居と同じだが、その裏面(店の内側)に板戸1枚を納められるほどの深さの决り欠き(しゃくり かき)をつくる。
夜間、店を閉じているとき、開口部を、上下2枚の板戸:蔀戸で閉じる。
開店時には、先の蔀梁の欠き込み部:戸袋に、上段の蔀戸を突き上げて納め、下段の蔀戸は、仕舞った上段の蔀戸の位置まで押上げ、ツマミを差し、止め置く(2枚の戸が並んで納まっている)。
この戸袋部を左右に仕切る束柱を箱束と呼び、蔀戸を滑らす溝が彫られている。
開口を閉じるとき、この箱束の下に、箱束と同じ断面の柱を立てる。この取外し自由な柱を閂と呼ぶ。
蔀梁は柱の外面から飛び出して取付くため、柱への枘を2枚に分け(二枚枘)、枘の先端を少し薄くして柱に差し、込み栓を打つ。このような先を薄くした枘をこき枘と呼ぶ。」
註 蔀梁の仕口を二枚枘とし、さらに先端を薄く斜めに殺ぐのは、枘孔の位置が柱の外面に近いため、
通常の枘で差すと、柱に亀裂が生じるおそれがあり、それを避けるための工夫と考えられます。
枘を上下2枚に分けるのも同じ理由だと思われます。
最後は出桁造り(だしげた づくり)の解説ですが、この紹介のために、揚戸を設けた商家の店先の断面図を載せます。
左側は「日本家屋構造」製図編にある出桁造りの商家の矩計図、右は近江八幡にある旧・西川家の矩計図(「重要文化財 旧西川家住宅修理工事報告書」より)。
Image may be NSFW.
Clik here to view.

先の第四十二図は、左側の商家についての解説と見なしてよいと思われます(ただ、この図では、箱束が壁で隠れています)。
右の西川家の例は、柱間が1間、ゆえに板戸は1列、2枚の例で、閂、箱束はありません。なお、西川家では、蔀戸ではなく摺り揚戸(すりあげ ど)と呼んでいます。蔀戸は、江戸の呼び方だったのかもしれません。
Image may be NSFW.
Clik here to view.

最後は、出桁造について。
この解説は上の矩計図を参照しつつお読みください。
「第二 出桁造り
第四十三図は、出桁造りの説明図。出桁造りは蔀造りの階上の造りに多く見られる。
図の甲は、肘木を取付けるための肘木受。肘木受は、肘木よりも高さは1寸5分以上大きく、厚さは2寸くらいとする。
註 肘木=腕木
図の乙は、柱間の中間で肘木受に取付く肘木の仕口。大きさは幅は柱と同寸、高さは柱径より3分ほど大きくする。仕口は大入れ蟻掛け。大入れは3〜4分。
柱に取付く肘木は、長枘を設け、柱に差し、先端は間柱まで伸ばし釘打ちとする。
図の丙は、出桁の姿図。出桁の大きさは、幅:柱の8/10×高さ:幅+3分。肘木に渡り欠きで架ける。
出桁の内側には、肘木の上端位置に小穴(こあな)を突き、図のように天井板を納める。
註 小穴 細い幅の溝。この場合は、板の厚さ分の幅、深さは板厚以上。溝を彫ることを突くという。
出格子(で ごうし)の出は、普通6寸以上8寸以下。柱は3寸角内外、上は肘木に枘差し・込み栓打ち、下端は頚切りをして瓦を嵌め込む。格子台の下端は瓦上端に置く。」
小屋組については、これで終りです。
次は縁側のつくりかたになります。