Image may be NSFW.
Clik here to view.
「環境」という立派な日本語があるのに、surroundings という英語で表記するのは、「環境」という語が、本来の意味をはずれ「うす汚れて」しまっているからです。
environment という surroundings 同様の意味を持つ英語もありますが、この語も「うす汚れて」しまっている気配があります( environmental design などという「不埒な」使い方さえあります)。
そこで、専門家を含め、多くの人が使わない(多分、学術的ひびき がないからだと思いますが)「きわめて平凡で、字義どおりに意味が分る」 surroundings を使って書くことにします。
註 環 たま、たまき、環形の玉。めぐる、めぐらす、わ。
境 さかい、領地、領内。特定のところ、場所。特定の状態、またその場合。
[白川 静 著「字通」]
環境 めぐりかこむ区域。あるものの周囲にあるもの、また、その行動する場所・状況。
あるものとの関係・影響をもつと考えられるもの。
[諸橋 轍次 他著「新漢和辞典」]
一週間ほど前、毎日新聞のコラムに「有名な」建築家へのインタビュー記事が載っていました。先に私が「理解不能」で挙げた人たちの一人です。
自ら自らを《前衛》と呼んで憚らない当人の発言もさりながら、私はインタビューを担当している記者の方の「感性」に「違和感」を感じ続けていました。
なぜなら、記者が日常身を置いている「自らの surroundings 」と「建築」とを、別扱いにしているように感じられたからです。
この記者にとっては、「建築(物)と surroundings は別の世界のもの」である、ということです。
そして、この「前衛家」も同じく「建築(物)と surroundings は別の世界のもの」である、と考えているとみてよいでしょう。
だからこそ、「理解不能」な発言が為されるのです(発言の内容は、「理解不能」で載せたコラムのコピーをお読みください)。
これは、記事を読んでの私の推測です。
「別扱いにしていない」のであれば、記事は別の内容になるはずです。
第一、この《前衛家》をインタビューの対象者とすることもないでしょう。
私は、これまでも書いてきたように、
建築(物)と surroundings は、別扱いはできない、別扱いにするのは間違いだ、
と考えています。
建築は、否応もなく、できあがると surroundings の一部になるのです。
と言うより、往時から、人びとは、人にとっての surroundings となるべく建築をつくってきた、
私の理解では、それが建築の歴史です。
しかし「建築(物)と surroundings は別の世界のもの」という「認識・理解」は、この記者や「前衛家」だけではなく、今、大方の方がたの「常識」になっているのかもしれません。だから、事物・事象に対して、本来なら最も鋭敏な神経を持つべき(私はそのように考えています)「記者」という職業の方でさえ、surroundings の存在、その意味について「無神経」になってしまっているのではないでしょうか。
もっとも、そういう記事を見かけたのが、この題材で書くことにしたきっかけではありますが・・・。
surroundings とは何か。
それについて、これまで、最も明解に日本語で語った のは道元である、と私は考えています。彼は、「近代」をはるかに超えていた、私はそう思います。
その言とは、何度も紹介している次の文言です。
・・・・
うを水をゆくに、ゆけども水のきはなく、
鳥そらをとぶに、とぶといへどもそらのきはなし。
しかあれども、
うをとり、いまだむかしよりみづそらをはなれず。
ただ用大のときは使大なり。要小のときは使小なり。・・・
鳥もし空をいづればたちまちに死す。
魚もし水をいづればたちまちに死す。
・・・・
つまり、surroundings とは、うをにとっての水、鳥にとっての空にほかなりません。
「人」も同じです。
私たち「人」は、surroundings の内で生きているのです。
すなわち、「人もし surroundings をいづればたちまちに死す」 ということです。
これまでの文章では、「空間」「居住空間」などと記してきました。
この「厳然たる事実」を、そこに浸っている、浸っているのが当たりまえである私たちは、それゆえに、気付かない、忘れてしまっている、のではないでしょうか。
慣れてしまうと感じなくなる、それは、怖ろしいことです。神経を逆なでする「建築物」や「街並み」「家並み」・・に日ごろ「囲まれ続けている」と、「逆なでされていること にさえも気付かなく」なります。
とりわけ、暮しも surroundings も都市化した場所で暮していると、それが当たりまえになります。
しかし、人であるかぎり、人びとの意識の内には、知らぬ間に「逆なでの結果」が鬱積するはずです。
その鬱積の塊りは、いったいどうなるのでしょう?
そして、「人もし surroundings をいづればたちまちに死す」という認識があったならば、一旦ことが起きたら取り返しのつかない surroundings となってしまうことを知りながら、「平和」利用で「安全だ」などと誤魔化して、原発をつくるようなこともしなかったはずです。できなかったはずです。
註 もっとも、道元は、 surroundings について特に言いたかったわけではありません。
道元は、より広く、「ものごとを表す文言を、字面どおりに理解してはならない」、
さらに言えば、言葉・文言の「限界」を認識せよ、
ということを言いたかったのだと思います(後掲記事参照)。
たとえば、
拍手とは、右の手と左の手を叩き合わせて音を出すこと、
そのとき、音を発したのは右手か左手か、というがごとき発問はやめよう、
と言えばよいかもしれません。
近代的学問の「方法」には、こういう手合いが多いように思いませんか?
このことを理解するのは、「近代的知」を「摺り込まれてしまった」現代の私たちにとって容易なことでない、のはよく分ります。
しかし、「人もし surroundings をいづればたちまちに死す」というのは、紛れもない事実、真実なのです。
何故この事実を認識できなくなってしまうのか、「 形の謂れ・補遺:form follows function 」 で書きました。
「認知症」という言葉があります。かつては「痴呆」と言っていました。
しかし「認知症」というのは日本語ではない。日本語になっていない。あえて言うならば「認知障碍」と言うべきだと思っています。
たしかに「痴呆」というのは人の心を逆なでします。「認知障害」でもそうでしょう。「害」の字がいけないのです。
しかし、「障碍」ならば、人を傷つけないはずです。
「碍」は「さまたげる」「さえぎる」「じゃまする」という意味。
電線の「碍子」は、電気が電線から他に流れないようにするための部品。
当用漢字に「碍」がない、そこで「害」の字が当てられてしまったのです。
「知的障害」と「知的障碍」では、意味がまったく違います。
現在も漢字を元通りに使っている台湾では、「残障者」が使われているそうです。
つまり、「認知障碍」とは、それまでの「普通の」「認知ができなくなった」状態。
何が「普通」なのか、別の問題が生じますが・・・。
「認知障碍」の方たちは、よく「徘徊する」と言われます。
そのイメージは、行方も定かでなく滅茶苦茶にほっつき歩く、というように聞こえます。しかし、そんなことはない。
もう大分前のことですが(確か以前に書いたような気もしますが)、初冬の冷たい雨がそぼ降る夕暮れどき、60代のはじめとおぼしき女性が突然訪ねてきました。当然雨に濡れています。
昔なじみを探している、どこだか分らなくなった、知らないか、というのです。その人に会うために、かつて歩いた(とおぼしき)道を、数キロも歩いてきたのです。
当然、私たちには分りません。電気ストーブを出して暖まってもらいながら、派出所に援けを求めました。
彼女は素足でした。靴下を履いていたのですが、靴下が濡れてしまうのを避けるためか、脱いで、かばんにしまってありました。昔気質なのです。足が凍えても、靴下が大事。衣料品が貴重品だった時代を過ごした方だと思います。
無事に住所を探してもらい、パトカーでおくり届けていただきました。
彼女は、いたずらに、いいかげんに歩いていたのではありません。ほっつき歩いていたのではないのです。
何がきっかけかは分りませんが、「ある情景」を思い出し、その昔通いなれた友だちの家を訪れることを思い立ったのです。
そのきっかけは、もしかしたら、初冬の夕暮れ時のある光景だったのかもしれません。
思いたったら、矢も盾もたまらず訪ねたくなったのではないでしょうか。心は完全に友だちとの世界に居るのです。冷たい雨に濡れながら、必死に歩いてきました。しかし、風景は変っている・・・。そして、たまたま明りの点いている当方を訪ねたのです。誰もそれを徘徊などといって批判することなどできません。
おそらく彼女の脳裏には、つまり目の前には、ある surroundings が見えていたのです。
それは、私たちが夢の中で見る情景・場景・状景・光景と同じです。
私たちの見る夢は、かならず surroundings をともなっているはずです。そしてそれは、「人もし surroundings をいづればたちまちに死す」ということが「事実」であることの紛れもない証でもあるのです。
そうなのです。彼女は、そのとき、「夢」の中にいたに違いありません。私たちの夢だって、変幻自在ではありませんか。あのとき、彼女の世界も変幻自在だったのです、きっと。
私たちがくたびれたとき、私たちの「本性」が表れます。認知障碍の方がたの「徘徊」が、それを顕にしてくれています。
私たちは、人は、生まれたときからずっと、surroundings の「中」にいます。このように、常に surroundings に囲まれているのです。出ることはできないのです。
私たちは、この「事実」を、そしてこの「事実」を認めたがらない、という事実をも、認めるべきではないでしょうか。
冒頭の図は、アルバー・アアルトのカレー邸のスケッチです。
彼が surroundings を設計していることが、このスケッチから分ります。これは、スケッチの一部です。もっと広い範囲の surroundings のスケッチもあります。
そして、このスケッチが図になったのが下の平面図です。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![]()
出典
THE LINE――ORIGINAL DRAWINGS from THE ALVAR AALTO ARCHIVE
MUSEUM of FINISH ARCHITECTURE 1993年 刊
現代建築の旗手とされるコルビュジェ、ミース・ファン・デル・ローエたちも、その初めのころの設計事例は、皆、 surroundings を設計しています。しかも、実に見事に・・・。
それが、いつごろから、どうして、中期・晩期の設計事例のようになったのか、その謂れについては詳しくは知りません。
しかしアアルトは、私の知る限り、 終生、surroundings の設計に徹しています。日本でも前川國男氏、村野藤吾氏、吉村順三氏などはそうではないか、と思います。
そして、これは大変重要なことだと私は思うのですが、
日本の近世までの建物づくりは、すべからく、階級を問わず、この日本という土地柄のなかで、 surroundings を整えることに徹してきた、と見ることができる、という事実です。
私は、それを、建物づくりとはモノをつくることではない、という意味で「心象風景をつくる」という言い方をしてきました。
それをものの見事に実現した、その数々の事例が私たちのまわりには、幸いなことに、まだたくさん在ります。
別の言い方をすれば、それらの事例に、この日本という風土・場所に暮す人たちの「暮しかた」、すなわち surroundings についての「見かた、考えかた」つまり「思想」が示されているはずなのです。
なぜ、それらに、それらに潜む surroundings についての「見かた、考えかた」つまり「思想」に、目を遣ることをしなくなったのでしょうか。
それらを、鑑賞の対象、モノとしてしか見ないなどというのは、私には、大変もったいない、と思えるのです。
これまでも、この点について、いろいろと書いてきましたが、あらためて視点を変えて、具体的に書いてみたいと思っています。
なぜなら、残念ながら、最近の多くの建築は、かつての人びとが、この風土の中で培ってきた「 surroundings についての思想」を忘れた設計になっているのではないか、私は、そのように、特に最近あらためて、痛切に、思っているからです。
Clik here to view.

「環境」という立派な日本語があるのに、surroundings という英語で表記するのは、「環境」という語が、本来の意味をはずれ「うす汚れて」しまっているからです。
environment という surroundings 同様の意味を持つ英語もありますが、この語も「うす汚れて」しまっている気配があります( environmental design などという「不埒な」使い方さえあります)。
そこで、専門家を含め、多くの人が使わない(多分、学術的ひびき がないからだと思いますが)「きわめて平凡で、字義どおりに意味が分る」 surroundings を使って書くことにします。
註 環 たま、たまき、環形の玉。めぐる、めぐらす、わ。
境 さかい、領地、領内。特定のところ、場所。特定の状態、またその場合。
[白川 静 著「字通」]
環境 めぐりかこむ区域。あるものの周囲にあるもの、また、その行動する場所・状況。
あるものとの関係・影響をもつと考えられるもの。
[諸橋 轍次 他著「新漢和辞典」]
一週間ほど前、毎日新聞のコラムに「有名な」建築家へのインタビュー記事が載っていました。先に私が「理解不能」で挙げた人たちの一人です。
自ら自らを《前衛》と呼んで憚らない当人の発言もさりながら、私はインタビューを担当している記者の方の「感性」に「違和感」を感じ続けていました。
なぜなら、記者が日常身を置いている「自らの surroundings 」と「建築」とを、別扱いにしているように感じられたからです。
この記者にとっては、「建築(物)と surroundings は別の世界のもの」である、ということです。
そして、この「前衛家」も同じく「建築(物)と surroundings は別の世界のもの」である、と考えているとみてよいでしょう。
だからこそ、「理解不能」な発言が為されるのです(発言の内容は、「理解不能」で載せたコラムのコピーをお読みください)。
これは、記事を読んでの私の推測です。
「別扱いにしていない」のであれば、記事は別の内容になるはずです。
第一、この《前衛家》をインタビューの対象者とすることもないでしょう。
私は、これまでも書いてきたように、
建築(物)と surroundings は、別扱いはできない、別扱いにするのは間違いだ、
と考えています。
建築は、否応もなく、できあがると surroundings の一部になるのです。
と言うより、往時から、人びとは、人にとっての surroundings となるべく建築をつくってきた、
私の理解では、それが建築の歴史です。
しかし「建築(物)と surroundings は別の世界のもの」という「認識・理解」は、この記者や「前衛家」だけではなく、今、大方の方がたの「常識」になっているのかもしれません。だから、事物・事象に対して、本来なら最も鋭敏な神経を持つべき(私はそのように考えています)「記者」という職業の方でさえ、surroundings の存在、その意味について「無神経」になってしまっているのではないでしょうか。
もっとも、そういう記事を見かけたのが、この題材で書くことにしたきっかけではありますが・・・。
surroundings とは何か。
それについて、これまで、最も明解に日本語で語った のは道元である、と私は考えています。彼は、「近代」をはるかに超えていた、私はそう思います。
その言とは、何度も紹介している次の文言です。
・・・・
うを水をゆくに、ゆけども水のきはなく、
鳥そらをとぶに、とぶといへどもそらのきはなし。
しかあれども、
うをとり、いまだむかしよりみづそらをはなれず。
ただ用大のときは使大なり。要小のときは使小なり。・・・
鳥もし空をいづればたちまちに死す。
魚もし水をいづればたちまちに死す。
・・・・
つまり、surroundings とは、うをにとっての水、鳥にとっての空にほかなりません。
「人」も同じです。
私たち「人」は、surroundings の内で生きているのです。
すなわち、「人もし surroundings をいづればたちまちに死す」 ということです。
これまでの文章では、「空間」「居住空間」などと記してきました。
この「厳然たる事実」を、そこに浸っている、浸っているのが当たりまえである私たちは、それゆえに、気付かない、忘れてしまっている、のではないでしょうか。
慣れてしまうと感じなくなる、それは、怖ろしいことです。神経を逆なでする「建築物」や「街並み」「家並み」・・に日ごろ「囲まれ続けている」と、「逆なでされていること にさえも気付かなく」なります。
とりわけ、暮しも surroundings も都市化した場所で暮していると、それが当たりまえになります。
しかし、人であるかぎり、人びとの意識の内には、知らぬ間に「逆なでの結果」が鬱積するはずです。
その鬱積の塊りは、いったいどうなるのでしょう?
そして、「人もし surroundings をいづればたちまちに死す」という認識があったならば、一旦ことが起きたら取り返しのつかない surroundings となってしまうことを知りながら、「平和」利用で「安全だ」などと誤魔化して、原発をつくるようなこともしなかったはずです。できなかったはずです。
註 もっとも、道元は、 surroundings について特に言いたかったわけではありません。
道元は、より広く、「ものごとを表す文言を、字面どおりに理解してはならない」、
さらに言えば、言葉・文言の「限界」を認識せよ、
ということを言いたかったのだと思います(後掲記事参照)。
たとえば、
拍手とは、右の手と左の手を叩き合わせて音を出すこと、
そのとき、音を発したのは右手か左手か、というがごとき発問はやめよう、
と言えばよいかもしれません。
近代的学問の「方法」には、こういう手合いが多いように思いませんか?
このことを理解するのは、「近代的知」を「摺り込まれてしまった」現代の私たちにとって容易なことでない、のはよく分ります。
しかし、「人もし surroundings をいづればたちまちに死す」というのは、紛れもない事実、真実なのです。
何故この事実を認識できなくなってしまうのか、「 形の謂れ・補遺:form follows function 」 で書きました。
「認知症」という言葉があります。かつては「痴呆」と言っていました。
しかし「認知症」というのは日本語ではない。日本語になっていない。あえて言うならば「認知障碍」と言うべきだと思っています。
たしかに「痴呆」というのは人の心を逆なでします。「認知障害」でもそうでしょう。「害」の字がいけないのです。
しかし、「障碍」ならば、人を傷つけないはずです。
「碍」は「さまたげる」「さえぎる」「じゃまする」という意味。
電線の「碍子」は、電気が電線から他に流れないようにするための部品。
当用漢字に「碍」がない、そこで「害」の字が当てられてしまったのです。
「知的障害」と「知的障碍」では、意味がまったく違います。
現在も漢字を元通りに使っている台湾では、「残障者」が使われているそうです。
つまり、「認知障碍」とは、それまでの「普通の」「認知ができなくなった」状態。
何が「普通」なのか、別の問題が生じますが・・・。
「認知障碍」の方たちは、よく「徘徊する」と言われます。
そのイメージは、行方も定かでなく滅茶苦茶にほっつき歩く、というように聞こえます。しかし、そんなことはない。
もう大分前のことですが(確か以前に書いたような気もしますが)、初冬の冷たい雨がそぼ降る夕暮れどき、60代のはじめとおぼしき女性が突然訪ねてきました。当然雨に濡れています。
昔なじみを探している、どこだか分らなくなった、知らないか、というのです。その人に会うために、かつて歩いた(とおぼしき)道を、数キロも歩いてきたのです。
当然、私たちには分りません。電気ストーブを出して暖まってもらいながら、派出所に援けを求めました。
彼女は素足でした。靴下を履いていたのですが、靴下が濡れてしまうのを避けるためか、脱いで、かばんにしまってありました。昔気質なのです。足が凍えても、靴下が大事。衣料品が貴重品だった時代を過ごした方だと思います。
無事に住所を探してもらい、パトカーでおくり届けていただきました。
彼女は、いたずらに、いいかげんに歩いていたのではありません。ほっつき歩いていたのではないのです。
何がきっかけかは分りませんが、「ある情景」を思い出し、その昔通いなれた友だちの家を訪れることを思い立ったのです。
そのきっかけは、もしかしたら、初冬の夕暮れ時のある光景だったのかもしれません。
思いたったら、矢も盾もたまらず訪ねたくなったのではないでしょうか。心は完全に友だちとの世界に居るのです。冷たい雨に濡れながら、必死に歩いてきました。しかし、風景は変っている・・・。そして、たまたま明りの点いている当方を訪ねたのです。誰もそれを徘徊などといって批判することなどできません。
おそらく彼女の脳裏には、つまり目の前には、ある surroundings が見えていたのです。
それは、私たちが夢の中で見る情景・場景・状景・光景と同じです。
私たちの見る夢は、かならず surroundings をともなっているはずです。そしてそれは、「人もし surroundings をいづればたちまちに死す」ということが「事実」であることの紛れもない証でもあるのです。
そうなのです。彼女は、そのとき、「夢」の中にいたに違いありません。私たちの夢だって、変幻自在ではありませんか。あのとき、彼女の世界も変幻自在だったのです、きっと。
私たちがくたびれたとき、私たちの「本性」が表れます。認知障碍の方がたの「徘徊」が、それを顕にしてくれています。
私たちは、人は、生まれたときからずっと、surroundings の「中」にいます。このように、常に surroundings に囲まれているのです。出ることはできないのです。
私たちは、この「事実」を、そしてこの「事実」を認めたがらない、という事実をも、認めるべきではないでしょうか。
冒頭の図は、アルバー・アアルトのカレー邸のスケッチです。
彼が surroundings を設計していることが、このスケッチから分ります。これは、スケッチの一部です。もっと広い範囲の surroundings のスケッチもあります。
そして、このスケッチが図になったのが下の平面図です。
Image may be NSFW.
Clik here to view.
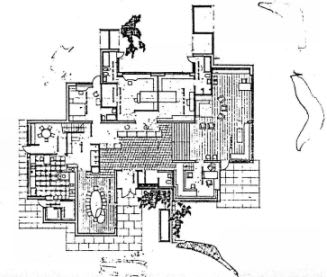
出典
THE LINE――ORIGINAL DRAWINGS from THE ALVAR AALTO ARCHIVE
MUSEUM of FINISH ARCHITECTURE 1993年 刊
現代建築の旗手とされるコルビュジェ、ミース・ファン・デル・ローエたちも、その初めのころの設計事例は、皆、 surroundings を設計しています。しかも、実に見事に・・・。
それが、いつごろから、どうして、中期・晩期の設計事例のようになったのか、その謂れについては詳しくは知りません。
しかしアアルトは、私の知る限り、 終生、surroundings の設計に徹しています。日本でも前川國男氏、村野藤吾氏、吉村順三氏などはそうではないか、と思います。
そして、これは大変重要なことだと私は思うのですが、
日本の近世までの建物づくりは、すべからく、階級を問わず、この日本という土地柄のなかで、 surroundings を整えることに徹してきた、と見ることができる、という事実です。
私は、それを、建物づくりとはモノをつくることではない、という意味で「心象風景をつくる」という言い方をしてきました。
それをものの見事に実現した、その数々の事例が私たちのまわりには、幸いなことに、まだたくさん在ります。
別の言い方をすれば、それらの事例に、この日本という風土・場所に暮す人たちの「暮しかた」、すなわち surroundings についての「見かた、考えかた」つまり「思想」が示されているはずなのです。
なぜ、それらに、それらに潜む surroundings についての「見かた、考えかた」つまり「思想」に、目を遣ることをしなくなったのでしょうか。
それらを、鑑賞の対象、モノとしてしか見ないなどというのは、私には、大変もったいない、と思えるのです。
これまでも、この点について、いろいろと書いてきましたが、あらためて視点を変えて、具体的に書いてみたいと思っています。
なぜなら、残念ながら、最近の多くの建築は、かつての人びとが、この風土の中で培ってきた「 surroundings についての思想」を忘れた設計になっているのではないか、私は、そのように、特に最近あらためて、痛切に、思っているからです。