Image may be NSFW.
Clik here to view.
今回は、「附録」から、「二十八 住家建築木材員数調兼仕様内訳調書」の項の紹介です。
原文を転載し、現代語で読み下すとともに、註記を付します。
転載部に註記してありますが、明治の初版本と大正版では、「表」の部分が異なります。
ただ、文章部分には、表題の「住家建築木材員数調兼仕様内訳調書」の調の字が大正版で省かれた以外には、変更箇所は見当たりません。「木材員数兼仕様内訳調書」で十分意味が通じます。
なお、原文転載部分に、行間の不揃いや歪みがあります。ご容赦ください。
原書は、現在ではきわめて稀な活版印刷です。そのためと思われますが、版面が各ページごとに若干異なっています。
たとえば、各行がページ上の波線に直交しているか、というと必ずしもそうとは限りません。しかも、波線自体、水平でもない・・・などなど。
編集は、「国会図書館蔵の明治37年刊の初版本の複写コピー」を基にしています。
編集作業は、一旦「原本の複写コピー」の各ページを更に複写コピーし、
読みやすいように、各項目ごとにまとまるように、ページ上の波線を基準線と見なしてA4用紙に切貼りし、
汚れている個所を消してスキャンする、という手順を踏んでいます。
こういった一連の操作の積み重ねが複合して、歪みや不揃いが生じてしまうようです。
もちろん、原文に改変などは一切加えてありません。念のため・・・。
**********************************************************************************************************
Image may be NSFW.
Clik here to view.
表の部分は「用語」の説明を加えるだけにいたします。
表中の用語の意味 (「日本建築辞彙 新訂版」による)
大正版 尺〆(しゃく じめ)
1尺角にして長さ2間、すなわち13尺なるを尺〆1本となす。これ木材に用うる単位なり。
もし奇零あらば尺〆何本何勺何才と称す。才の位より以下用うること稀なり。
才(さい)
? 1寸角にして長さ6尺なるを1才という。これは板子などを売買するときに用うる単位なり。
?勺〆1本の1/100をいう。即ち130立法寸なり。
これは粗木(あらき)の売買に尺〆の奇零(単位以下、即ち小数点以下の意)として用いらるるものなり。
註 現在の木材の材長で多用される4mは、13尺の読替えによるもの。
現在の建材の規格は、大半が尺貫法時代の規格の読替えであった。
ただし、多くはいわゆる関東間対応であるため、京間など関西の用には適していない。
尺貫法時代の規格寸法には、すべて「現場」の裏付け、つまり謂れがあった。
残念ながら、現在、金属建具の〈新規格〉のように、謂れを欠いた《標準化》が進行している。
なお、大正版表中の杭木の項「朱口」は「末口(すえくち)」の誤植と解します。
以下、本文部分を現代文で読み下します。
使用する材料等の員数調べは「表」の如くに記入し、その順序、及び部位名あるいは材料名を次に挙げる。
註 「木材」員数とありますが、「木材」以外も示されています。
また、「材料」とありますが、各部に使う材料:「部材」の意味と解します。
部材名を部位ごとに分け、たとえば差敷居、差鴨居を「軸組まわり」に移すなど、原文の順序ではなく、私なりに、まとめ直します。
なお、矩計図を参考のために再掲します。
Image may be NSFW.
Clik here to view.
主屋の部
差鴨居・軒桁〜小屋組まわり
軒桁 小屋梁 小屋束 小屋貫 棟木 母屋 野隅木 谷木 野垂木 化粧垂木 広小舞 鼻隠 裏板 野地板
屋根葺下地まわり
瓦桟 土居葺 杮板 軒唐草止木 土居土止木
註 ここでは瓦葺の名がありませんが、「二十九 仕様書の一例」(次回紹介予定)では具体的記載があります。
軸組まわり
土台 柱 差敷居 差鴨居 貫(通し貫 壁塗り込み貫) 大引 床束(大引受) 根搦貫(ねがらみぬき)
註 原文の根柵貫を、現在の一般的表記の根搦貫に改めました。「日本建築辞彙」では、根緘=根搦とあり根柵の表記はありません。
床(ゆか)まわり
根太 敷居 畳寄せ 床板(ゆかいた)
造作
鴨居 付鴨居 長押 床框 床柱 落掛 床板(とこいた) 地板(ぢいた) 袋戸棚板 違い棚板 欄間敷居・鴨居 天井長押 回縁 竿縁
註 「床の間」まわりの構造については、「『日本家屋構造』の紹介−17」を参照ください。
天井まわり
釣木受 釣木 裏桟 天井板
註 「天井」まわりの構造については、「『日本家屋構造』の紹介−18」を参照ください。
縁側の部
化粧:造作
縁框 根太 縁板 無目 一筋鴨居 同所綿板 垂木掛 化粧垂木 淀 広小舞 木小舞 裏板 野垂木 野地板 屋根葺材(杮板または鉄板)
註 上ば野地の垂木:野垂木、>(上ば野地の)裏板:野地板、屋根:屋根葺材の意と解します。
外まわり
土台上雨押え 窓下雨押え 窓上横板庇の板 同猿頭 下見板受下縁 下見板 同押縁簓子
板庇
腕木 腕桁 庇板 目板 垂木形 品板(しな いた) 面戸 鼻搦(はな がらみ) 雨押え 恵降板(えぶり いた) 笠木
註 品板(しな いた):下図参照 鼻搦(はな がらみ):下図参照 恵振板(えぶり いた):絵振板、柄振板 などとも書く。下図参照。
図は「日本建築辞彙 新訂版」より転載。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![]()
出格子
柱 妻板 格子台 鴨居第 格子
戸袋
柱 妻板 上下長押 皿板 中桟 戸袋板 目板 台輪
註 皿板:戸袋の底板のこと
便所
土台 柱 桁 根太 床板 巾木板 無目 窓敷居 窓鴨居 小脇の方立 天井回縁 同竿縁 床下柱内側横板
外まわり土台上
雨押え 窓下雨押え 横板庇など
地形(地業)
水杭 水貫 水縄 山留用杭 同堰板 割栗石 切込砂利 布石 柱下玉石 束石 大小便所の甕 同所の叩き土、石灰など
地形(地業)用語の参考図を再掲します。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![]()
**********************************************************************************************************
次回は、製図篇の最終章「二十九 普通住家建築仕様書の一例」の紹介。分量が多いので数回に分けるかもしれません。
Clik here to view.
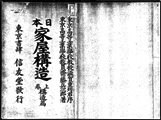
今回は、「附録」から、「二十八 住家建築木材員数調兼仕様内訳調書」の項の紹介です。
原文を転載し、現代語で読み下すとともに、註記を付します。
転載部に註記してありますが、明治の初版本と大正版では、「表」の部分が異なります。
ただ、文章部分には、表題の「住家建築木材員数調兼仕様内訳調書」の調の字が大正版で省かれた以外には、変更箇所は見当たりません。「木材員数兼仕様内訳調書」で十分意味が通じます。
なお、原文転載部分に、行間の不揃いや歪みがあります。ご容赦ください。
原書は、現在ではきわめて稀な活版印刷です。そのためと思われますが、版面が各ページごとに若干異なっています。
たとえば、各行がページ上の波線に直交しているか、というと必ずしもそうとは限りません。しかも、波線自体、水平でもない・・・などなど。
編集は、「国会図書館蔵の明治37年刊の初版本の複写コピー」を基にしています。
編集作業は、一旦「原本の複写コピー」の各ページを更に複写コピーし、
読みやすいように、各項目ごとにまとまるように、ページ上の波線を基準線と見なしてA4用紙に切貼りし、
汚れている個所を消してスキャンする、という手順を踏んでいます。
こういった一連の操作の積み重ねが複合して、歪みや不揃いが生じてしまうようです。
もちろん、原文に改変などは一切加えてありません。念のため・・・。
**********************************************************************************************************
Image may be NSFW.
Clik here to view.

表の部分は「用語」の説明を加えるだけにいたします。
表中の用語の意味 (「日本建築辞彙 新訂版」による)
大正版 尺〆(しゃく じめ)
1尺角にして長さ2間、すなわち13尺なるを尺〆1本となす。これ木材に用うる単位なり。
もし奇零あらば尺〆何本何勺何才と称す。才の位より以下用うること稀なり。
才(さい)
? 1寸角にして長さ6尺なるを1才という。これは板子などを売買するときに用うる単位なり。
?勺〆1本の1/100をいう。即ち130立法寸なり。
これは粗木(あらき)の売買に尺〆の奇零(単位以下、即ち小数点以下の意)として用いらるるものなり。
註 現在の木材の材長で多用される4mは、13尺の読替えによるもの。
現在の建材の規格は、大半が尺貫法時代の規格の読替えであった。
ただし、多くはいわゆる関東間対応であるため、京間など関西の用には適していない。
尺貫法時代の規格寸法には、すべて「現場」の裏付け、つまり謂れがあった。
残念ながら、現在、金属建具の〈新規格〉のように、謂れを欠いた《標準化》が進行している。
なお、大正版表中の杭木の項「朱口」は「末口(すえくち)」の誤植と解します。
以下、本文部分を現代文で読み下します。
使用する材料等の員数調べは「表」の如くに記入し、その順序、及び部位名あるいは材料名を次に挙げる。
註 「木材」員数とありますが、「木材」以外も示されています。
また、「材料」とありますが、各部に使う材料:「部材」の意味と解します。
部材名を部位ごとに分け、たとえば差敷居、差鴨居を「軸組まわり」に移すなど、原文の順序ではなく、私なりに、まとめ直します。
なお、矩計図を参考のために再掲します。
Image may be NSFW.
Clik here to view.

主屋の部
差鴨居・軒桁〜小屋組まわり
軒桁 小屋梁 小屋束 小屋貫 棟木 母屋 野隅木 谷木 野垂木 化粧垂木 広小舞 鼻隠 裏板 野地板
屋根葺下地まわり
瓦桟 土居葺 杮板 軒唐草止木 土居土止木
註 ここでは瓦葺の名がありませんが、「二十九 仕様書の一例」(次回紹介予定)では具体的記載があります。
軸組まわり
土台 柱 差敷居 差鴨居 貫(通し貫 壁塗り込み貫) 大引 床束(大引受) 根搦貫(ねがらみぬき)
註 原文の根柵貫を、現在の一般的表記の根搦貫に改めました。「日本建築辞彙」では、根緘=根搦とあり根柵の表記はありません。
床(ゆか)まわり
根太 敷居 畳寄せ 床板(ゆかいた)
造作
鴨居 付鴨居 長押 床框 床柱 落掛 床板(とこいた) 地板(ぢいた) 袋戸棚板 違い棚板 欄間敷居・鴨居 天井長押 回縁 竿縁
註 「床の間」まわりの構造については、「『日本家屋構造』の紹介−17」を参照ください。
天井まわり
釣木受 釣木 裏桟 天井板
註 「天井」まわりの構造については、「『日本家屋構造』の紹介−18」を参照ください。
縁側の部
化粧:造作
縁框 根太 縁板 無目 一筋鴨居 同所綿板 垂木掛 化粧垂木 淀 広小舞 木小舞 裏板 野垂木 野地板 屋根葺材(杮板または鉄板)
註 上ば野地の垂木:野垂木、>(上ば野地の)裏板:野地板、屋根:屋根葺材の意と解します。
外まわり
土台上雨押え 窓下雨押え 窓上横板庇の板 同猿頭 下見板受下縁 下見板 同押縁簓子
板庇
腕木 腕桁 庇板 目板 垂木形 品板(しな いた) 面戸 鼻搦(はな がらみ) 雨押え 恵降板(えぶり いた) 笠木
註 品板(しな いた):下図参照 鼻搦(はな がらみ):下図参照 恵振板(えぶり いた):絵振板、柄振板 などとも書く。下図参照。
図は「日本建築辞彙 新訂版」より転載。
Image may be NSFW.
Clik here to view.

出格子
柱 妻板 格子台 鴨居第 格子
戸袋
柱 妻板 上下長押 皿板 中桟 戸袋板 目板 台輪
註 皿板:戸袋の底板のこと
便所
土台 柱 桁 根太 床板 巾木板 無目 窓敷居 窓鴨居 小脇の方立 天井回縁 同竿縁 床下柱内側横板
外まわり土台上
雨押え 窓下雨押え 横板庇など
地形(地業)
水杭 水貫 水縄 山留用杭 同堰板 割栗石 切込砂利 布石 柱下玉石 束石 大小便所の甕 同所の叩き土、石灰など
地形(地業)用語の参考図を再掲します。
Image may be NSFW.
Clik here to view.

**********************************************************************************************************
次回は、製図篇の最終章「二十九 普通住家建築仕様書の一例」の紹介。分量が多いので数回に分けるかもしれません。