Image may be NSFW.
Clik here to view.
今回は、「二十二 附属建物 土蔵」の項。
はじめに、原書の文と図を編集して転載します(歪みや不揃いなどがあります。ご容赦ください)。
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Image may be NSFW.
Clik here to view. 以下、現代語で読み下し、随意、註を付します。
以下、現代語で読み下し、随意、註を付します。
住家(すまいや:住居)は、光線、空気の流通などに留意するが、土蔵は、専ら(もっぱら)防火に意を尽くす。切妻造とするのが通例である。第二十六〜二十八図は土蔵の構造の概要を示した図である。
註 この図だけでは分りにくいので、実例として、かつて紹介した近江八幡にある「旧・西川家の土蔵」の図と写真を再掲します。
Image may be NSFW.
Clik here to view.
土蔵を建築するにあたっては、先ず、建設する場所の地質に適応した地形(ぢぎょう:現在は地業と表記)を行い、地盤石(ぢばんいしorぢばんせき:礎石のこと)を四周に据え、側石(がわいし)を積み重ね、土台を受ける。
註 「日本建築辞彙」では、「側石」=「根石」=「蠟燭石」と解説されているが、第二十六図の場合は、「布石」と解する方が適切ではないか。
蠟燭石などは、下記に説明があります。
「日本家屋構造・中巻の紹介−4」
側石の上に土台を据える。
土台は、下端および外面に柿渋あるいはコールタール(ともに防腐剤)を塗る。
柱には、その外面に苆掛け(すさかけ:塗壁の芯材となる小舞竹:こまいたけ:を受けるための段状、簓:ささら:状の刻み)を刻む。刻みの間隔は4〜5寸程度。
苆掛け:先の「旧西川家の土蔵」中の図に参考図があります。
苆:すさorつた:塗壁の材料の土や漆喰など:の、乾燥後の亀裂を防ぐために混入する繊維状の材料。
従来は自然の品:古藁、古麻布、棕櫚など:が使われたが、最近はガラス繊維も用いられる。
柱は三尺間隔で建てることが多い。
また、両妻の柱は伸ばして母屋を差し、天秤梁を枘差しまたは折置として、その前後に繋ぎ梁を差し、地棟(丑梁)及び天秤梁との仕口は渡腮(わたりあご)及び蟻掛(ありかけ)とする。
註 図がないので、このままでは意が分りません。そこで、次のように解釈します。
妻面には、@3尺に柱を建て、中央にあたる柱2本の間に地棟を受ける天秤梁を掛ける。
例1 梁行2間:12尺のときは柱を@3尺で5本建て、2本目と4本目の柱の間に天秤梁を組み込む。
天秤梁を組み込まずに、中央にあたる3本目の柱で直接地棟(丑梁)を承けることもできるが、架構の強度は天秤梁を組み込む方が強い。
この場合は、天秤梁の代りに、各柱を貫あるいは差鴨居で固めることも考えられる。
なお、旧・西川家の土蔵では、2本目〜4本目に天秤梁を組み込み、3本目の柱も天秤梁を承けている(前掲の写真、断面図参照)。
例2 梁行2間半:15尺ならば、たとえば、@3尺で柱を6本建て3本目、4本目の柱間3尺に天秤梁を組み込み、地棟を承ける。
いずれにせよ、妻面の架構の強度を考慮してあれば、妻面の梁の構成は任意である。
天秤梁は、柱上に折置か、あるいは、2本の柱の間に枘差で取付く。
地棟と天秤梁の仕口は、渡腮及び蟻掛とする。
これは「京呂組:兜蟻掛け」の意と解します。
これについては「日本家屋構造の紹介−11」の第三十七図を参照ください。
なお、下記中の図および解説も参照ください。
「日本家屋構造・中巻の紹介−7」
「日本家屋構造の紹介−13」
小屋中の合掌は、軒先を折置として、地棟上にて組合せ、左右の束及び傍軒垂木ともみな苆掛けを切り刻む。
註 左右の束とは、妻面の天秤梁上の母屋承けに束柱を設ける場合の意と解します。
垂木は、軒桁上で止め、鉢巻貫及び広小舞を打つ。野地は裏板として垂木上面に張り、瓦葺き用の土居葺きを施す。裏板には、縄掛貫及び土止木を打付ける。
註 この部分は、第二十六図の乙図を参照。
裏板は、室内の天井板になる。
貫は、@2尺程度に平屋建てならば、中央一通り、二階建てのときは二通り、掛子彫(かけこぼり)にして、柱の貫穴に渡腮で納めるか、あるいは込栓打ちで固める。
註 「中央」の意が分りません。
掛子彫とは、貫を貫穴に渡腮で架けるための欠き込みの意と解します。
楔を打つと、貫と貫穴が噛み合い、簡単には動かなくなります。
なお、柱内で貫を交叉させ、双方の貫の交叉部を相欠きとし、楔打ちによって両者を噛み合わせる方法を採ることがあります。
一例は「日本の建物づくりを支えてきた技術−19」」参照。
込栓打ち:貫を所定の位置に通した後、柱外面から込栓を打つ。
要は、柱と貫を、強固な格子状に組むための方策です。
壁下地の小舞は、木材の時は1寸2〜3分角の材を使い、防腐のために柿渋またはコールタール塗とする。
竹を用いるときは、周長4〜5寸程度のものを、縦は柱間に5本ずつ、横は苆掛ごとに釘打ちで取付け、棕櫚縄(しゅろなわ)あるいは蕨縄(わらびなわ:蕨の根の筋でつくった縄)を本大和(ほんやまと)あるいは片大和(かたやまと)に纏わせる(巻きつける)。
註 本大和、片大和:竹などに、縄や蔓を纏わせる:巻きつける:ことの呼称。本大和は両方から、片大和は片方一方だけの巻き方。
なぜ「大和」と呼ぶのか、謂れが分りません。
「小舞を掻く」とのように、通常、小舞に縄を巻きつけることを「掻く」と呼んでいる。
平壁の土付の厚さ:土塗壁の厚さ:は小舞外面より4寸以上5〜6寸程度とする。
屋根は、6寸勾配ほどで、普通は瓦葺とするが、地域によっては、土居塗をした後、その上に猫石を据え、別途合掌を組み、杮葺(こけらぶき)または茅葺の屋根を設ける場合がある。
これを鞘(さや、あるいは鞘組:さやぐみ)と呼び、土居塗を保護するための手法である。
註 鞘組の屋根を瓦葺にする例の方が多いかもしれない。
猫石:一般には、土台を地面などから隔てるために据える石を称する。なぜ「ねこ」と呼ぶのか、謂れは知りません。もしかして「根子」かな?
猫石を据えず、直接合掌を土居塗上に流している例を見た記憶があります。
また、土居塗と鞘の屋根との間の空隙は、インシュレーションとしても効果的のようです。
土蔵入口下部に設ける煙返石(けむがえしいし)は、高さ7寸〜7寸5分程度、上端:上面の幅は木柄戸(きがらど:土蔵の扉のこと)の厚さにもよるが、8寸内外とする。
註 煙返石:扉の下部からの煙・熱風:火炎の侵入を防ぐために設ける。
第二十七図・甲のように、石と扉、扉と枠及び扉相互の召合せ部は、空気・煙が流れにくいように段状に仕上げる。これを掛子塗(かけごぬり)と呼ぶ。
木柄戸:土蔵の扉は、木造骨組の上に漆喰を塗り込める。この骨組を木柄(きがら)と呼ぶ。
以下は第二十六図参照。
腰巻の高さは腰無目の上端までとし、腰巻下端の出は、鉢巻の棚角を垂直に下した位置を腰巻受石の外面とする。受石の高さは4寸以上7〜8寸ぐらいとする。
鉢巻の高さは、その建物により、恰好よく定めるが、下端の出は2寸ぐらい、その勾配は2〜2寸5分の返し勾配とする。
註 原本第二十六図の矩計図では、垂木を軒桁で止めているが、旧・西川家の土蔵のように、垂木は軒桁よりも可能な限り外側に出すのが普通。
鉢巻は、その垂木の出を土塗で覆うための方策。それにより、土塗部の荷重を、垂木も担うことになる(西川家の土蔵の図参照)。
第二十六図の仕様では、鉢巻部を、それより下の土壁が支えることになり、亀裂・崩落を生じやすくなる。
なお、煉瓦造では、その部分を、その部分を蛇腹で納めている(「形の謂れ−1・・・・軒蛇腹」参照)。
折釘(おりくぎorおれくぎ)の位置は、上段の釘は、鉢巻の下端から6〜7寸下げ、下段は腰巻上端から1尺2寸ぐらい上げ、中段は雨押えより7〜8寸離して打つ。
註 折釘:維持・管理のための事前の用意。折釘間に足場丸太を架ける。それゆえ、間隔等は、それに応じる。
したがって、設置高さに一定値があるわけではなく、建物の規模などに応じて勘案するものと考えられる。
火災時には、架けた丸太に塩かます(莚:むしろ:を二つ折りして塩を入れた袋)を掛けたという(水を吸い、燃えにくいため)。
普通の筵よりも目が積んでいる。架けるときは、広げて一枚にする。かつては、霜解け、雪解けの道に敷いたりもした。
入口の高さは、煙返石の上端から刀刃(かたなば)の下端までを6尺〜6尺2寸ぐらいとし(第二十六図・矩計参照)、横幅は刀刃の内法で3尺6寸ぐらいにするのが普通である(第二十七図・甲、入口平面参照)。
註 刀刃:土蔵その他「塗家」に於いて、入口または窓の脇に取付けたる三角形の縁木にして漆喰塗の止まりとなるもの(「日本建築辞彙・新訂版」より)。
要は漆喰塗の見切縁。第二十七図・甲の左辺参照。
このような形にするのは、縁と漆喰塗の接触面を増やして離れを少なくし、また、離れが生じても見えにくくする現場の知恵と考えられる。
入口を形づくる実柱(さねばしら、さねはしら)は、4寸5分角を用い、その外面を土塗壁の仕上り面と同じにし、左右の開きは、本柱の入口側面〜実柱内面を土壁の厚さ程の位置に設ける(第二十七図・甲参照)。実柱と本柱は、櫓貫(やぐらぬき)を前後から打ち込み、縫う。櫓貫は、幅4寸5分×厚1寸、5分ぐらいの勾配で楔状に加工する(第二十六図参照)。
兜桁(かぶとげた:高さ5寸×幅4寸5分)の高さは、楣下端〜桁下端を9寸〜1尺ぐらい、鼻の長さは、開いたとの幅と同じにする(第二十七図・丙参照)。
扉の肘壷(ひじつぼ)の位置は、下部は、木柄戸の下から1尺ぐらいをその下端とし、上部のそれは、木柄戸の上端から6寸ぐらい下がった位置に設ける。
木柄戸の下端は、煙返石下端より1寸5分上げ、上端は刀刃外すなわち楣下端までとする。また、木柄戸の前面の出は、壁の塗上がり面と同じ、内面は、煙返石との距離を8分〜1寸明きとする(第二十六、二十七図参照)。
木柄戸の釣り込みは、開閉を容易にするため、上方を3分ぐらい垂直より内側に釣り込む。
窓枠は4寸角でつくる。上枠の鼻の長さは、先の兜桁にならう。
窓の木柄戸の長さ(高さ)は、本屋の上下の刀刃の外法間の長さととし、木柄戸の上端を上の刀刃上端より3分ぐらい高い位置に取付ける。
窓の木柄戸の肘壷の位置は、下は戸の下端から6寸ぐらい上げ、上は戸の上端から4寸ぐらい下げの位置とする。
刀刃の大きさは、入口まわりは、2寸2分くらい、窓まわりは1寸8分ぐらいの(直角)三角形とする。
入口の木柄戸の縦框:2寸5分×2寸2分、上下横桟(框):3寸2分×2寸2分、中桟:2寸5分×1寸4分、筋違:2寸5分×1寸4分、簑貫(みのぬき):杉6分板赤身幅2寸ぐらいを用いる。
窓の木柄戸の縦框:2寸×1寸5分、上下横桟:2寸2分×1寸5分、中桟・筋違:2寸×1寸、簑貫:杉4分板赤身を用いる。
註 簑貫:土蔵の扉に用いる貫を言う。
**********************************************************************************************************
以上で「土蔵」の項は終りです。
次回は、「二十三 冠木門(かぶきもん)」「二十四 腕木門(うできもん)」「二十五 塀重門(へいじゅうもん)」の項を予定しています。
Clik here to view.
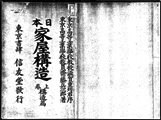
今回は、「二十二 附属建物 土蔵」の項。
はじめに、原書の文と図を編集して転載します(歪みや不揃いなどがあります。ご容赦ください)。
Image may be NSFW.
Clik here to view.

Image may be NSFW.
Clik here to view.

Image may be NSFW.
Clik here to view.
 以下、現代語で読み下し、随意、註を付します。
以下、現代語で読み下し、随意、註を付します。住家(すまいや:住居)は、光線、空気の流通などに留意するが、土蔵は、専ら(もっぱら)防火に意を尽くす。切妻造とするのが通例である。第二十六〜二十八図は土蔵の構造の概要を示した図である。
註 この図だけでは分りにくいので、実例として、かつて紹介した近江八幡にある「旧・西川家の土蔵」の図と写真を再掲します。
Image may be NSFW.
Clik here to view.

土蔵を建築するにあたっては、先ず、建設する場所の地質に適応した地形(ぢぎょう:現在は地業と表記)を行い、地盤石(ぢばんいしorぢばんせき:礎石のこと)を四周に据え、側石(がわいし)を積み重ね、土台を受ける。
註 「日本建築辞彙」では、「側石」=「根石」=「蠟燭石」と解説されているが、第二十六図の場合は、「布石」と解する方が適切ではないか。
蠟燭石などは、下記に説明があります。
「日本家屋構造・中巻の紹介−4」
側石の上に土台を据える。
土台は、下端および外面に柿渋あるいはコールタール(ともに防腐剤)を塗る。
柱には、その外面に苆掛け(すさかけ:塗壁の芯材となる小舞竹:こまいたけ:を受けるための段状、簓:ささら:状の刻み)を刻む。刻みの間隔は4〜5寸程度。
苆掛け:先の「旧西川家の土蔵」中の図に参考図があります。
苆:すさorつた:塗壁の材料の土や漆喰など:の、乾燥後の亀裂を防ぐために混入する繊維状の材料。
従来は自然の品:古藁、古麻布、棕櫚など:が使われたが、最近はガラス繊維も用いられる。
柱は三尺間隔で建てることが多い。
また、両妻の柱は伸ばして母屋を差し、天秤梁を枘差しまたは折置として、その前後に繋ぎ梁を差し、地棟(丑梁)及び天秤梁との仕口は渡腮(わたりあご)及び蟻掛(ありかけ)とする。
註 図がないので、このままでは意が分りません。そこで、次のように解釈します。
妻面には、@3尺に柱を建て、中央にあたる柱2本の間に地棟を受ける天秤梁を掛ける。
例1 梁行2間:12尺のときは柱を@3尺で5本建て、2本目と4本目の柱の間に天秤梁を組み込む。
天秤梁を組み込まずに、中央にあたる3本目の柱で直接地棟(丑梁)を承けることもできるが、架構の強度は天秤梁を組み込む方が強い。
この場合は、天秤梁の代りに、各柱を貫あるいは差鴨居で固めることも考えられる。
なお、旧・西川家の土蔵では、2本目〜4本目に天秤梁を組み込み、3本目の柱も天秤梁を承けている(前掲の写真、断面図参照)。
例2 梁行2間半:15尺ならば、たとえば、@3尺で柱を6本建て3本目、4本目の柱間3尺に天秤梁を組み込み、地棟を承ける。
いずれにせよ、妻面の架構の強度を考慮してあれば、妻面の梁の構成は任意である。
天秤梁は、柱上に折置か、あるいは、2本の柱の間に枘差で取付く。
地棟と天秤梁の仕口は、渡腮及び蟻掛とする。
これは「京呂組:兜蟻掛け」の意と解します。
これについては「日本家屋構造の紹介−11」の第三十七図を参照ください。
なお、下記中の図および解説も参照ください。
「日本家屋構造・中巻の紹介−7」
「日本家屋構造の紹介−13」
小屋中の合掌は、軒先を折置として、地棟上にて組合せ、左右の束及び傍軒垂木ともみな苆掛けを切り刻む。
註 左右の束とは、妻面の天秤梁上の母屋承けに束柱を設ける場合の意と解します。
垂木は、軒桁上で止め、鉢巻貫及び広小舞を打つ。野地は裏板として垂木上面に張り、瓦葺き用の土居葺きを施す。裏板には、縄掛貫及び土止木を打付ける。
註 この部分は、第二十六図の乙図を参照。
裏板は、室内の天井板になる。
貫は、@2尺程度に平屋建てならば、中央一通り、二階建てのときは二通り、掛子彫(かけこぼり)にして、柱の貫穴に渡腮で納めるか、あるいは込栓打ちで固める。
註 「中央」の意が分りません。
掛子彫とは、貫を貫穴に渡腮で架けるための欠き込みの意と解します。
楔を打つと、貫と貫穴が噛み合い、簡単には動かなくなります。
なお、柱内で貫を交叉させ、双方の貫の交叉部を相欠きとし、楔打ちによって両者を噛み合わせる方法を採ることがあります。
一例は「日本の建物づくりを支えてきた技術−19」」参照。
込栓打ち:貫を所定の位置に通した後、柱外面から込栓を打つ。
要は、柱と貫を、強固な格子状に組むための方策です。
壁下地の小舞は、木材の時は1寸2〜3分角の材を使い、防腐のために柿渋またはコールタール塗とする。
竹を用いるときは、周長4〜5寸程度のものを、縦は柱間に5本ずつ、横は苆掛ごとに釘打ちで取付け、棕櫚縄(しゅろなわ)あるいは蕨縄(わらびなわ:蕨の根の筋でつくった縄)を本大和(ほんやまと)あるいは片大和(かたやまと)に纏わせる(巻きつける)。
註 本大和、片大和:竹などに、縄や蔓を纏わせる:巻きつける:ことの呼称。本大和は両方から、片大和は片方一方だけの巻き方。
なぜ「大和」と呼ぶのか、謂れが分りません。
「小舞を掻く」とのように、通常、小舞に縄を巻きつけることを「掻く」と呼んでいる。
平壁の土付の厚さ:土塗壁の厚さ:は小舞外面より4寸以上5〜6寸程度とする。
屋根は、6寸勾配ほどで、普通は瓦葺とするが、地域によっては、土居塗をした後、その上に猫石を据え、別途合掌を組み、杮葺(こけらぶき)または茅葺の屋根を設ける場合がある。
これを鞘(さや、あるいは鞘組:さやぐみ)と呼び、土居塗を保護するための手法である。
註 鞘組の屋根を瓦葺にする例の方が多いかもしれない。
猫石:一般には、土台を地面などから隔てるために据える石を称する。なぜ「ねこ」と呼ぶのか、謂れは知りません。もしかして「根子」かな?
猫石を据えず、直接合掌を土居塗上に流している例を見た記憶があります。
また、土居塗と鞘の屋根との間の空隙は、インシュレーションとしても効果的のようです。
土蔵入口下部に設ける煙返石(けむがえしいし)は、高さ7寸〜7寸5分程度、上端:上面の幅は木柄戸(きがらど:土蔵の扉のこと)の厚さにもよるが、8寸内外とする。
註 煙返石:扉の下部からの煙・熱風:火炎の侵入を防ぐために設ける。
第二十七図・甲のように、石と扉、扉と枠及び扉相互の召合せ部は、空気・煙が流れにくいように段状に仕上げる。これを掛子塗(かけごぬり)と呼ぶ。
木柄戸:土蔵の扉は、木造骨組の上に漆喰を塗り込める。この骨組を木柄(きがら)と呼ぶ。
以下は第二十六図参照。
腰巻の高さは腰無目の上端までとし、腰巻下端の出は、鉢巻の棚角を垂直に下した位置を腰巻受石の外面とする。受石の高さは4寸以上7〜8寸ぐらいとする。
鉢巻の高さは、その建物により、恰好よく定めるが、下端の出は2寸ぐらい、その勾配は2〜2寸5分の返し勾配とする。
註 原本第二十六図の矩計図では、垂木を軒桁で止めているが、旧・西川家の土蔵のように、垂木は軒桁よりも可能な限り外側に出すのが普通。
鉢巻は、その垂木の出を土塗で覆うための方策。それにより、土塗部の荷重を、垂木も担うことになる(西川家の土蔵の図参照)。
第二十六図の仕様では、鉢巻部を、それより下の土壁が支えることになり、亀裂・崩落を生じやすくなる。
なお、煉瓦造では、その部分を、その部分を蛇腹で納めている(「形の謂れ−1・・・・軒蛇腹」参照)。
折釘(おりくぎorおれくぎ)の位置は、上段の釘は、鉢巻の下端から6〜7寸下げ、下段は腰巻上端から1尺2寸ぐらい上げ、中段は雨押えより7〜8寸離して打つ。
註 折釘:維持・管理のための事前の用意。折釘間に足場丸太を架ける。それゆえ、間隔等は、それに応じる。
したがって、設置高さに一定値があるわけではなく、建物の規模などに応じて勘案するものと考えられる。
火災時には、架けた丸太に塩かます(莚:むしろ:を二つ折りして塩を入れた袋)を掛けたという(水を吸い、燃えにくいため)。
普通の筵よりも目が積んでいる。架けるときは、広げて一枚にする。かつては、霜解け、雪解けの道に敷いたりもした。
入口の高さは、煙返石の上端から刀刃(かたなば)の下端までを6尺〜6尺2寸ぐらいとし(第二十六図・矩計参照)、横幅は刀刃の内法で3尺6寸ぐらいにするのが普通である(第二十七図・甲、入口平面参照)。
註 刀刃:土蔵その他「塗家」に於いて、入口または窓の脇に取付けたる三角形の縁木にして漆喰塗の止まりとなるもの(「日本建築辞彙・新訂版」より)。
要は漆喰塗の見切縁。第二十七図・甲の左辺参照。
このような形にするのは、縁と漆喰塗の接触面を増やして離れを少なくし、また、離れが生じても見えにくくする現場の知恵と考えられる。
入口を形づくる実柱(さねばしら、さねはしら)は、4寸5分角を用い、その外面を土塗壁の仕上り面と同じにし、左右の開きは、本柱の入口側面〜実柱内面を土壁の厚さ程の位置に設ける(第二十七図・甲参照)。実柱と本柱は、櫓貫(やぐらぬき)を前後から打ち込み、縫う。櫓貫は、幅4寸5分×厚1寸、5分ぐらいの勾配で楔状に加工する(第二十六図参照)。
兜桁(かぶとげた:高さ5寸×幅4寸5分)の高さは、楣下端〜桁下端を9寸〜1尺ぐらい、鼻の長さは、開いたとの幅と同じにする(第二十七図・丙参照)。
扉の肘壷(ひじつぼ)の位置は、下部は、木柄戸の下から1尺ぐらいをその下端とし、上部のそれは、木柄戸の上端から6寸ぐらい下がった位置に設ける。
木柄戸の下端は、煙返石下端より1寸5分上げ、上端は刀刃外すなわち楣下端までとする。また、木柄戸の前面の出は、壁の塗上がり面と同じ、内面は、煙返石との距離を8分〜1寸明きとする(第二十六、二十七図参照)。
木柄戸の釣り込みは、開閉を容易にするため、上方を3分ぐらい垂直より内側に釣り込む。
窓枠は4寸角でつくる。上枠の鼻の長さは、先の兜桁にならう。
窓の木柄戸の長さ(高さ)は、本屋の上下の刀刃の外法間の長さととし、木柄戸の上端を上の刀刃上端より3分ぐらい高い位置に取付ける。
窓の木柄戸の肘壷の位置は、下は戸の下端から6寸ぐらい上げ、上は戸の上端から4寸ぐらい下げの位置とする。
刀刃の大きさは、入口まわりは、2寸2分くらい、窓まわりは1寸8分ぐらいの(直角)三角形とする。
入口の木柄戸の縦框:2寸5分×2寸2分、上下横桟(框):3寸2分×2寸2分、中桟:2寸5分×1寸4分、筋違:2寸5分×1寸4分、簑貫(みのぬき):杉6分板赤身幅2寸ぐらいを用いる。
窓の木柄戸の縦框:2寸×1寸5分、上下横桟:2寸2分×1寸5分、中桟・筋違:2寸×1寸、簑貫:杉4分板赤身を用いる。
註 簑貫:土蔵の扉に用いる貫を言う。
**********************************************************************************************************
以上で「土蔵」の項は終りです。
次回は、「二十三 冠木門(かぶきもん)」「二十四 腕木門(うできもん)」「二十五 塀重門(へいじゅうもん)」の項を予定しています。