《![]()
今回は、「縁側及化粧之部」「間内之部」「外廻り下見張り之部」の項の紹介。原文を再掲します。
![]()
以下、註を交えながら、読み下します。
なお、文中の用語・部位名称・位置の分る縁側の矩計図を再掲します。
![]()
縁側及び化粧の部
本屋の柱径をAとして表記します。
縁桁:長さ2間のとき、
角材の場合は、成(高さ) 1.5〜1.6A×幅 1.1A
丸太の場合は、末口径6寸以上
縁框:長さ9尺〜2間のとき、成(高さ) 4寸〜4寸5分×幅 2寸5分〜3寸
長さ2間〜3間のとき、成(高さ) 5寸〜6寸以上×幅 3寸5分〜4寸
縁板:幅3寸以上、4・5寸、厚7・8分位
根太:長さ3尺(=縁側幅)のとき、二寸角
長さ4尺(=縁側幅)のとき、成(高さ) 2寸5分×幅 2寸(原文「二寸に二寸五分角」をこのように解します)
縁板:幅3寸以上4・5寸、厚7・8分位
無目:成(高さ) 1寸8分以上2寸2分、幅 0.9A
一筋鴨居:成(高さ) 2寸以上3寸、幅 2寸以上2寸2分
垂木掛: 成(高さ) 0.8A×幅 0.45A
化粧垂木:成(高さ) 1寸5〜6分以上2寸×幅 1寸4分以上1寸6〜7分
淀:幅 3寸、厚 7〜8分
広小舞:幅 4寸以上 5寸、厚1寸以上 1寸5〜6分
木小舞:成 7〜8分、但し淀の厚と同じ、幅 8分以上1寸2分
裏板(化粧天井板):杉四分板または「へぎ板」
註 「へぎ板」、薄く削いだ板
野垂木:松三寸(成 1寸5分、厚 1寸2分くらい)又は二寸角
註 松三寸:呼称、通称か?
野地(板):六分板又は三寸貫
註 六分板:墨掛厚六分なる板をいう。実寸は四分五厘程(≒13.6mm)にして、幅一尺以内、長さ一間なり。(再掲)
三寸貫(さんずん ぬき):長さ二間、幅三寸、厚さ七分の杉材をいう。その実寸は幅一寸六分〜二寸二分、厚さ三分五厘〜五分なり。(再掲)
屋根:杮葺き、鉄板葺き及び瓦葺きなど
間内の部(室内各部の木割)
本屋の柱径をAとして表記
敷居:幅は柱幅に同じ、すなわち A、成(高さ)は 2寸。ただし、縁側に付ける敷居は幅0.95A
畳寄(たたみよせ):成は敷居に同じ
鴨居:成 0.35A〜0.4A×幅 0.9A
付鴨居(つけがもい):鴨居と同じ
内法長押:成 0.8A〜 0.9A,0.95A、幅は柱より成の1/5出す
小壁吊束:0.8A角
欄間の敷居、鴨居:ともに、幅 0.65Aまたは0.7A、厚 0.25A
天井長押:成 0.6まAたは0.65A
天井回縁:成 0.5A、下端の出は、長押に同じ、すなわち柱より成の1/5出す
天井竿縁:0.3A角、または成 0.3A×幅 0.25A(原文の「三分に二分半」をこのように解しました)
以下床の間まわりの木割の説明になりますので、「構造編」で紹介した床の間についての原文を再掲します。
![]()
![]()
![]()
床柱:角柱の場合は、見付(みつき、みつけ:正面)を他の柱より少し大きくする
丸柱の場合は、末口径を、他の柱の大きさ程度にする
床框(とこがまち):成 1A、幅 0.85A
落掛(おとしがけ):成 0.5Aまたは 0.55A、幅 0.7Aまたは 0.8A
袋戸棚及び地板:板厚 0.3A
違棚:板厚 0.2Aまたは 0.25A(=Bとする)
海老束(えびづか):√2B角
海老束の面取り:束の径の 1/7 相当を几帳面とする
海老束の位置:板の前面より束一個分ほど内側
板の出:海老束左右の面から束一個分ほど、あるいは板厚の2倍ほどでも可
筆返し:出は板木口(端部)より板厚(B)ほど、高さは 1.5B、幅は海老束の芯または内面まで(図参照)
違い棚の落差:下板下端〜上板上端=A(柱径)程度とする
註 この木割に従えば、一定程度は「見慣れた床の間まわりの姿」になります。しかし、それがその部屋に適切であるかどうかは別問題です。
実際は、部屋の状況に応じて任意に造られています。「任意」は、造る人の「感性」に委ねられています。
外回り、下見張りの部
以下は、再掲した矩計図を参照ください。
土台上及び敷居下の雨押(あまおさえ):幅 2寸または2寸5分、厚 1寸ぐらい、一番大貫の二つ割も可
註 一番大貫:大貫のなかでも、赤身無節、角が端正なものをいう
大貫:杉大貫は、長さ二間、幅四寸、厚さ一寸の墨掛なり。実寸は幅三寸九分、厚さ八、九分程なり。・・・
窓上の横板庇:1寸板
同所の猿頭(さるかしら):1寸に1寸4〜5分
簓子縁(ささらこぶち):普通は杉の大小割(おおこわり)正1寸×1寸2分、平縁(ひらぶち)の場合は大貫の二つ割または中貫(ちゅうぬき)の二つ割
註 大小割:墨掛の大きさ一寸五分に一寸二分なる矩形木口の杉材にして、長さ二間なり。
平縁:断面が矩形なる薄き押縁木をいう。これを天井及び下見に用う。
大貫:前掲
中貫:杉中貫は、長さ二間、幅三寸五分、厚さ八分とす。尤もこれは墨掛寸法なる故、実寸は、幅三寸二、三分、厚さ六分〜六分五厘程なり。
(以上「日本建築辞彙」新訂版より)
板:杉または檜の生小節(いきこぶし)または無節のものを用いる
註 生節(きぶし):固く付着し居りて、形のくずれざる節をいう。
小節(こぶし):木材に在りて、差渡し径四、五分程度の節が、長さ二間につき一方に二、三ヶ所以内あるものを、小節材または小節と略称す。
上小節(じょうこぶし)は差渡し二、三分程迄の節が前記同様にあるものなり。 (以上「日本建築辞彙」新訂版より)
以上で「普通住家略木割」の章の紹介は終りです。
**********************************************************
当時の家屋は、現在とは異なり、小屋裏(屋根裏)、床下、壁内部などの他は、ほとんどすべての材が仕上がり後も目に触れるのが普通でしたから、部材寸法に神経を使っていました(現在でも「真壁」仕様では同様です)。
そして、仕上がり後の姿、見えがかりの姿の良し悪しは、造る人たちの感性に委ねられていた、と言ってよく、したがって、人によって結果に大きな差が生まれます。
そこで、誰がやっても一定程度の仕上がりになることを考えて生まれたのがいわゆる「木割」であった、と考えられます。要するに「安直な手引書」です。おそらく、職方の経験・知見とその伝承の集積がまとめられたものと思われます。
ただ、このような「木割」:「手引書」が生まれると、個々の職方が独自に考えることの障害になり、形式化しがちです。「こうしておけばいい」のだと思われるようになり、甚だしい場合は「こうでなければならない」とさえ思われるようになります(「法令を順守してさえいればいい」という現在の「風潮」に通じるところがあります)。「つくるにあたって、何を考えなければならないのか」という「根本的な視点」:「radicalな視点」が問われなくなる、「radicalな思考」を欠く傾向を生むのです。
有名な木割書に「匠明」というのがあります。「建築史研究者」の中には、その指示する木割に従っていない建物は劣るものだと見なす方がたがいます。
これなども、「radicalな思考」を欠いた例と言えるでしょう。
「木割」の示す諸数値は、あくまでも「参考値」なのです。その数値で実際に図を描き、自らの感覚でその当否を判断する・・・、そうすることで、自らの感覚を養う、その「一つの出発点」と考えるのが無難なのではないか、と私は思います。
一度、「匠明」の木割で図を描いてみたことがあります。少なくとも私の感覚では「異様な姿」になったことを覚えています。
**********************************************************
次回から「小屋組」、各種「屋根」の章になります。
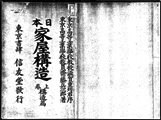
今回は、「縁側及化粧之部」「間内之部」「外廻り下見張り之部」の項の紹介。原文を再掲します。

以下、註を交えながら、読み下します。
なお、文中の用語・部位名称・位置の分る縁側の矩計図を再掲します。

縁側及び化粧の部
本屋の柱径をAとして表記します。
縁桁:長さ2間のとき、
角材の場合は、成(高さ) 1.5〜1.6A×幅 1.1A
丸太の場合は、末口径6寸以上
縁框:長さ9尺〜2間のとき、成(高さ) 4寸〜4寸5分×幅 2寸5分〜3寸
長さ2間〜3間のとき、成(高さ) 5寸〜6寸以上×幅 3寸5分〜4寸
縁板:幅3寸以上、4・5寸、厚7・8分位
根太:長さ3尺(=縁側幅)のとき、二寸角
長さ4尺(=縁側幅)のとき、成(高さ) 2寸5分×幅 2寸(原文「二寸に二寸五分角」をこのように解します)
縁板:幅3寸以上4・5寸、厚7・8分位
無目:成(高さ) 1寸8分以上2寸2分、幅 0.9A
一筋鴨居:成(高さ) 2寸以上3寸、幅 2寸以上2寸2分
垂木掛: 成(高さ) 0.8A×幅 0.45A
化粧垂木:成(高さ) 1寸5〜6分以上2寸×幅 1寸4分以上1寸6〜7分
淀:幅 3寸、厚 7〜8分
広小舞:幅 4寸以上 5寸、厚1寸以上 1寸5〜6分
木小舞:成 7〜8分、但し淀の厚と同じ、幅 8分以上1寸2分
裏板(化粧天井板):杉四分板または「へぎ板」
註 「へぎ板」、薄く削いだ板
野垂木:松三寸(成 1寸5分、厚 1寸2分くらい)又は二寸角
註 松三寸:呼称、通称か?
野地(板):六分板又は三寸貫
註 六分板:墨掛厚六分なる板をいう。実寸は四分五厘程(≒13.6mm)にして、幅一尺以内、長さ一間なり。(再掲)
三寸貫(さんずん ぬき):長さ二間、幅三寸、厚さ七分の杉材をいう。その実寸は幅一寸六分〜二寸二分、厚さ三分五厘〜五分なり。(再掲)
屋根:杮葺き、鉄板葺き及び瓦葺きなど
間内の部(室内各部の木割)
本屋の柱径をAとして表記
敷居:幅は柱幅に同じ、すなわち A、成(高さ)は 2寸。ただし、縁側に付ける敷居は幅0.95A
畳寄(たたみよせ):成は敷居に同じ
鴨居:成 0.35A〜0.4A×幅 0.9A
付鴨居(つけがもい):鴨居と同じ
内法長押:成 0.8A〜 0.9A,0.95A、幅は柱より成の1/5出す
小壁吊束:0.8A角
欄間の敷居、鴨居:ともに、幅 0.65Aまたは0.7A、厚 0.25A
天井長押:成 0.6まAたは0.65A
天井回縁:成 0.5A、下端の出は、長押に同じ、すなわち柱より成の1/5出す
天井竿縁:0.3A角、または成 0.3A×幅 0.25A(原文の「三分に二分半」をこのように解しました)
以下床の間まわりの木割の説明になりますので、「構造編」で紹介した床の間についての原文を再掲します。



床柱:角柱の場合は、見付(みつき、みつけ:正面)を他の柱より少し大きくする
丸柱の場合は、末口径を、他の柱の大きさ程度にする
床框(とこがまち):成 1A、幅 0.85A
落掛(おとしがけ):成 0.5Aまたは 0.55A、幅 0.7Aまたは 0.8A
袋戸棚及び地板:板厚 0.3A
違棚:板厚 0.2Aまたは 0.25A(=Bとする)
海老束(えびづか):√2B角
海老束の面取り:束の径の 1/7 相当を几帳面とする
海老束の位置:板の前面より束一個分ほど内側
板の出:海老束左右の面から束一個分ほど、あるいは板厚の2倍ほどでも可
筆返し:出は板木口(端部)より板厚(B)ほど、高さは 1.5B、幅は海老束の芯または内面まで(図参照)
違い棚の落差:下板下端〜上板上端=A(柱径)程度とする
註 この木割に従えば、一定程度は「見慣れた床の間まわりの姿」になります。しかし、それがその部屋に適切であるかどうかは別問題です。
実際は、部屋の状況に応じて任意に造られています。「任意」は、造る人の「感性」に委ねられています。
外回り、下見張りの部
以下は、再掲した矩計図を参照ください。
土台上及び敷居下の雨押(あまおさえ):幅 2寸または2寸5分、厚 1寸ぐらい、一番大貫の二つ割も可
註 一番大貫:大貫のなかでも、赤身無節、角が端正なものをいう
大貫:杉大貫は、長さ二間、幅四寸、厚さ一寸の墨掛なり。実寸は幅三寸九分、厚さ八、九分程なり。・・・
窓上の横板庇:1寸板
同所の猿頭(さるかしら):1寸に1寸4〜5分
簓子縁(ささらこぶち):普通は杉の大小割(おおこわり)正1寸×1寸2分、平縁(ひらぶち)の場合は大貫の二つ割または中貫(ちゅうぬき)の二つ割
註 大小割:墨掛の大きさ一寸五分に一寸二分なる矩形木口の杉材にして、長さ二間なり。
平縁:断面が矩形なる薄き押縁木をいう。これを天井及び下見に用う。
大貫:前掲
中貫:杉中貫は、長さ二間、幅三寸五分、厚さ八分とす。尤もこれは墨掛寸法なる故、実寸は、幅三寸二、三分、厚さ六分〜六分五厘程なり。
(以上「日本建築辞彙」新訂版より)
板:杉または檜の生小節(いきこぶし)または無節のものを用いる
註 生節(きぶし):固く付着し居りて、形のくずれざる節をいう。
小節(こぶし):木材に在りて、差渡し径四、五分程度の節が、長さ二間につき一方に二、三ヶ所以内あるものを、小節材または小節と略称す。
上小節(じょうこぶし)は差渡し二、三分程迄の節が前記同様にあるものなり。 (以上「日本建築辞彙」新訂版より)
以上で「普通住家略木割」の章の紹介は終りです。
**********************************************************
当時の家屋は、現在とは異なり、小屋裏(屋根裏)、床下、壁内部などの他は、ほとんどすべての材が仕上がり後も目に触れるのが普通でしたから、部材寸法に神経を使っていました(現在でも「真壁」仕様では同様です)。
そして、仕上がり後の姿、見えがかりの姿の良し悪しは、造る人たちの感性に委ねられていた、と言ってよく、したがって、人によって結果に大きな差が生まれます。
そこで、誰がやっても一定程度の仕上がりになることを考えて生まれたのがいわゆる「木割」であった、と考えられます。要するに「安直な手引書」です。おそらく、職方の経験・知見とその伝承の集積がまとめられたものと思われます。
ただ、このような「木割」:「手引書」が生まれると、個々の職方が独自に考えることの障害になり、形式化しがちです。「こうしておけばいい」のだと思われるようになり、甚だしい場合は「こうでなければならない」とさえ思われるようになります(「法令を順守してさえいればいい」という現在の「風潮」に通じるところがあります)。「つくるにあたって、何を考えなければならないのか」という「根本的な視点」:「radicalな視点」が問われなくなる、「radicalな思考」を欠く傾向を生むのです。
有名な木割書に「匠明」というのがあります。「建築史研究者」の中には、その指示する木割に従っていない建物は劣るものだと見なす方がたがいます。
これなども、「radicalな思考」を欠いた例と言えるでしょう。
「木割」の示す諸数値は、あくまでも「参考値」なのです。その数値で実際に図を描き、自らの感覚でその当否を判断する・・・、そうすることで、自らの感覚を養う、その「一つの出発点」と考えるのが無難なのではないか、と私は思います。
一度、「匠明」の木割で図を描いてみたことがあります。少なくとも私の感覚では「異様な姿」になったことを覚えています。
**********************************************************
次回から「小屋組」、各種「屋根」の章になります。