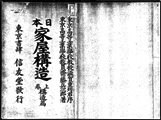
「構造編」のタイトルを継続使用します。
紹介に入る前に
ここしばらく、このブログに、「日本家屋」の「各部の名称」や「各部の構造」(「つくりかた」か?)を調べるために(?)寄られる方が大勢居られます。建築系の学校で夏休みの宿題でも出されたのかな、などと訝っています。
そして、この「現象」を見るにつけ、「日本家屋構造・上巻」を紹介する際に、先ずはじめに書いておくべきことがあった、とあらためて思いましたので、遅まきながら、中巻を紹介するにあたって書いておくことにします。
それは、「日本家屋構造」を「教科書」として「日本の家屋・建築」について学ぼうとした人びと、つまり学生たちが生きていた社会が、どういう社会であったか、ということについてです。
一言でいえば、この「教科書」に取り上げられている各種の「事例」は、明治年間には、どの地域でも普通に見られる「事例」であった、つまり、学生たちは、各部の「名称」や「構造」は知らなくても、そこに載っている「事例」の存在をよく知っていた、決して珍しいものではなかったのです。
さらに言えば、学生たちの身の回りには、江戸時代に建てられた家屋はもとより、それ以前に建てられた例も、数は少ないとはいえ、あったはずです。大げさに言えば、身の回りに古今の建物が、重層的に蓄積され、存在していたのです(それが、人の暮す「家並」「街並」の本来の姿なのです)。
この書の事例に違和感なく接することができるのは、
かつて、「文化度の高い:cultivated な地域」(後註参照)で暮していた、ある年代より上の方がたか、
現在、「文化度の高い:cultivated な地域」にお住いの方がた
そして、そういう場所で暮してはいないが、そのような地域やそこにある建物群を意識的に観てきた方がた、
に限られるのではないでしょうか。
では、今、この書のなかみに触れる若い方がたはどうでしょうか?
おそらく、そこに載っている各種の図面は、身の回りで見たことがない事例についての図がほとんどでしょう。
もちろん、どの地域に住まわれているかによって異なります。
しかし、少なくとも大都会では、身の回りには見かけることはなく、博物館か郷土資料館にでも行かなければ見ることもできないでしょう(それさえもかなわないかもしれません)。
つまり、身の回りで目にすることとは関係ないため、見ても実感がともなわないのです。
都市化の進んだ地域の若い方がたが身の回りで目にするもの、それは住宅メーカーのつくる建物であり、たまに「木造家屋」があっても、それは、現行の法規に拠った「かつての日本家屋、日本建築とは(意図的に)縁を切ったつくりの建物」。まして、古今の建物が目の前に実在するなどということはまずない。目にする事例すべてが、前代と断絶している。
千葉県・佐倉にある「歴史民俗博物館」はお勧めです。「家屋」だけではなく「古建築」全般にわたり知ることができます(大縮尺の模型も多数あります)。
しかし、幸いなことに、大都会を離れれば、あるいは、「都市化・近代化に遅れたとされる」地域に行けば、古今の断絶を感じないで済む地域がまだ多数残っています。そういう地域に住まわれている方がたは、明治の若者と同じく、この書の内容に違和感を感じることはないはずです。
私は、大都会を離れ、「都市化・近代化に遅れたとされる」地域を「文化度の高い:cultivated な地域」と考えています。
逆に、都市化の進んだ地域、たとえば、東京の「発展地」:「地価の高騰地域」は、「文化度が低い」と見なします。
なぜなら、そこで目にする建物は、その多くが、「根無し」。
・・・・・
(われわれを取り囲むのは)まがいものの建築、すなわち模倣、すなわち虚偽(Sham Architecture;i.e.,imitation;i.e.,lying)」(i.e.=that is:すなわち)・・・・
「われわれも両親も祖父母も、かつてなかったような忌むべき環境(surroundings)に生活してきた。・・・・
虚偽が法則(rule)となり、真実(truth)は例外となっている。・・・・
これは、19世紀末のヨーロッパの建築についてのオランダの建築家ベルラーヘが語った言葉です(「まがいもの・模倣・虚偽からの脱却」参照)。
今の日本の都会はまさにこの姿に重なります。
もちろん、「文化度の高い:cultivated な地域」は、大都会・東京でも皆無ではありません。
根岸や谷中のあたりにゆけば、体験することができます。そのほかにも点在してはいます。
そして、「日本家屋」の「各部の名称」や「各部の構造」を学びたいのであれば、先ず、そういう地域・場所へ出向き、実際の事例を観察するのが必須ではないか、とも考えます。
いったい、目の前の建物は、どうしてこのような「平面」になっているのか、「形」になっているのか、・・・・そして、いったいどのような手順でつくるのか、・・・・その場で観ながら考える。「名称」を知るのは、それからでも遅くはないのではないでしょうか。
もしも、「各部の名称を調べてこい」、などという「宿題」が出されていたとするならば、それは、「教育」として間違っている、と私は思います。
なんなら、「対象」を写生:スケッチし(写真ではダメ)、それを持って、図書館、博物館、資料館を訪ね、書物を紐解いたり、あるいは学芸員や司書に教えを乞う、これが最高の「学習」ではないか、と私は考えます。大工さんに訊けたら最高ですね!
書物を読んで集めただけの「知識」は「知恵」にならない、と思っています。サンテグジュペリならずとも、それでは「辞書」と同じだ!
・・・・
私が山と言うとき、私の言葉は、
茨で身を切り裂き、断崖を転落し、岩にとりついて汗にぬれ、その花を摘み、
そしてついに、絶頂の吹きさらしで息をついたおまえに対してのみ、
山を言葉で示し得るのだ。
言葉で示すことは把握することではない。
・・・・
・・・・
言葉で指し示すことを教えるよりも、
把握することを教える方が、はるかに重要なのだ。
ものをつかみとらえる操作のしかたを教える方が重要なのだ。
おまえが私に示す人間が、なにを知っていようが、
それが私にとってなんの意味があろう?それなら辞書と同様である。
・・・・ サン・テグジュペリ「城砦」(みすず書房)より
写真ではなぜダメか。それは、「対象」を観ないからです。ファインダーを見ているだけになるからです。
前置きが長くなりました。以下、「日本家屋構造・中巻・製図編」の紹介に入ります。
**********************************************************
「目次」は以下の通り。


この書で言う「製図」は、「設計」という意味も含まれています。
それについて触れているのが、「一 総論」です。以下が原文です。



字が小さく、文体も現在と異なりますので読みにくいと思います。
そこで、現在の文体で、私なりに読み下すことにします。
一 総論
人が家屋を構造する(構築する、つくる)のは、単に雨露を防ぐためではなく、宝貨什器(家財)を保護し、生活を愉快に送れるようにするためである。
愉快の感を得るのは、経済的堅牢的要素よりも、衛生便利に適合する家屋に於いてである。
建物が如何に壮麗であっても、不便利で採光換気が当を得ていなければ、快楽を感じることはあり得ない。
家屋を建設しようとするには、これらの点に留意し、先ず、建設地の地質の良否、辺景(周辺の景観・環境)の如何、採光・換気、間取りから給排水に至るまで切に研究すべきである。
〇地質
高燥(こうそう:高地で湿気の少ない)で砂層の土地は、住家に適する。
かつての池沼が埋没した低地や両側を丘陵に挟まれた一帯の低地、その他一般に低地で粘土質の土地は健康に適さない。
低地は悪水(あくすい:飲用など利用に適さない水)が滞留しやすく、しかも粘土質の土は熱を吸収することが少なく、湿気を吸収しやすく、重さで百分の二に達することもある。
ゆえに、粘土質の地は寒く湿気も多いが、砂層の地は暖かく湿気も少ない。
註 高燥な砂層の土地 おそらく、関西地方の真砂(まさ):花崗岩の砕けた砂の地質:をイメージしているのでは?
しかし、東京をはじめ関東地方は火山灰:ローム:で覆われていて砂層の場所は少ない。
粘土質の土地 真砂やロームでも、微細になって堆積し水分と圧力が加われば粘土質の土壌になる。
江戸末には、比高の高い地区は大半が居住地になっていた。それゆえ、明治になり、都市へ集まりだした人びとが選べる場所は、低地しかなかった。
この解説は、そういう状況を踏まえて、家屋は、比高の高い場所に建てるのが望ましく、低地、池沼の埋立などもってのほか、と説いていると考えてよい。
現代は、このような「常識」も失われてしまったようです(液状化現象の多発した新興住宅地は、池沼、海岸埋立地が多い)。
〇辺景
土地を自由に選択できる所ならば人造的(人工的)風致をつくることも可能ではある。
しかし、周囲に在る天然の風景をいかに利用するかは建築設計者の責務である。
眺望が広々とひらけ、新鮮な空気を存分に吸い精神を爽快にすることほど愉快なことはない。これこそ、住まいをつくることの目的(の一つ)である。
しかし、市中の商賈(しょうこ:商人)の町のように、常に塵埃を生じ、あるいは高い建物で光線を遮られるような場所に住戸をつくらざるを得ない場合は、窓や間取りを工夫し、空気の流通を完全にし、なるべく多くの光線を採りいれるようなつくりかたを考えなければならない。
註 建設地の気候や風向きに応じて新鮮な空気と陽光を採りいれることが重大留意点であることは、基本的に、現在でも変らないはずである。
今は、それらをすべて「機械的に」処理しようとする。室内を閉め切り常時機械換気をせよ、などという恐るべき発想の法規まである・・・。
現在の教科書なら、「省エネ」「断熱」・・などが説かれるところだろう・・・。
〇方位
我が国は、全般に、夏季は東南風、冬季は北西風が多いが、地域によっては山脈の方向、海岸線の如何によって風向きは異なる。また、気候寒熱の度合いに応じて家屋の位置・方向を異にすべきである。
我が国のような温暖な地域では大差はないけれども、家屋の位置如何により、不都合が生じることがあるので、位置を慎重に選択して、風の向きによる室内空気の流通に配慮し、樹木を植えるなど夏時に襲来する暴風のための防備を設けることも肝要である。
註 建設地の風向きの特徴は、周辺の既存集落の様態(防風林の位置、建物の建て方、・・など)から知ることができる。
〇間取り
住家の内部は、一つの都市のようなものである。
都市には、公共の性質を有する建物、個人に属する建物、公共の道路、公園があるごとく、住家に於いても、応接室、客間、階段、廊下、便所などの他人が入ることはもちろん、装飾などを施して来客を歓迎する趣向を為す場所がある一方、居間、台所、押入、物置などのように、外来者の入ることを許さない性質の場所もある。
しかし、宏廈(こうか:広く大きな住家)に於いて完全に室を配置しようとすると数十種の室を要するだろう。
しかし、現今の中等以上の住家の場合は、玄関、脱帽室、応接室、客間、次の間、主人居間、次の間、主婦居間、次の間、寝間、老人室(としよりのま)、仏間、茶の間、子供部屋、書斎、書生室、下女部屋、下男室、台所、湯殿、便所、物置、土蔵、などを要するだろう。
ただし、これは家族数により斟酌すべきことで、別冊参考図を参照のこと。
註 別冊参考図とは「日本家屋構造・下巻・図面編」を指しています。
下巻に所載の各様の「住家平面図」は、分量の関係で、後日紹介させていただくことにします。
「住家の内部は尚一都市におけるか如し・・・」という言は、現在の「住居論」「建築計画学」・・などでも語られない見かたではないでしょうか。
ただ、それが、なぜ、「表座敷主体」の間取りに連なるのか、分りません。
あるいは、旧東京駅のつくりに表れているように、都市に対する見かたもこれに似ていたのかもしれません。
また、
ここにいう「居間」は、現在の意味と多少異なります。「主人居間」「主婦居間」:主人、主婦が普段いる部屋・・・・、
現在の居間に相当するのは、「茶の間」か。
この説明および以下の各室の説明は、中等以上の武家住宅を下敷きにしていた当時の(中等の)住家の様態と思われます。
武家住宅、とりわけ中等以上の場合、「家」意識はあっても、「家族」の意識は薄かったと考えられます。
なお、武家住宅で、「家族」が普段どこにいたのか:「家族の居間」がどこであったのか、よく分りません。ご存知の方、ご教示ください。
以下、各室について
「玄関」
玄関は、家屋正面に位して、衆目の集注し、その品格を表す所なので、不体裁なく、厳粛に構えることが求められる。その方位(向き)は、東南あるいは東方が良いが北に向うのも良いとされる。
「客間」
客間は賓客をここに誘い(いざない)、談話応接し、あるいは饗宴などに使用する一種の表座敷とし、家屋の中で最も肝要な室であるから、空気の流通をよくし、方位を選び、辺景を利用し、内部に(床の間、違い棚などの)装飾を施し、前面に庭園を設けるのを常とする。その方位は南面するを良しとする。
ただ、南面すると、客に植物の裏を観せることになるので北面にするのが良い、という説もあるが、客の来訪時間は不定であり、北面する客間は陰気になってかえって客に不快感を抱かせることの方が多いだろう。
装飾は、床の間、違い棚には、掛物、花瓶、香箱、置物などを陳列し、欄間には彫刻を施し、書院を設け、その障子は美術的障子組子にする・・など。
註 ここでの「書院」は「付書院」のこと。
「次の間」
次の間は、主要な室に連なり、平時は襖をもって仕切り、宴会など多人数が集まるとき、襖を取り払い一広間とする場合の備える。「二の間」「三の間」などを設ける場合もある。また、襖に描かれる絵画の名をとって室名にすることもある。
註 これは、「書院造」、「客殿」を下敷きにした様態である。
「書斎」
書斎は閑静な所で、東あるいは東南が良い。
「台所」
台所は、食物を調理する場所なので、清潔にして、下婢(かひ:下女)の働くのに便利な位置がよく、採光、換気に留意する。
北向きは冬季寒冷で日航が直射することがないので、板の間などの湿気が乾きにくい。西向きは日光の直射が強く、夏時は調理用火気とあいまち炎熱堪えがたく、食物の腐敗も早まる。
「廊下」など
廊下は、通風採光十分にして、来客が通行の際、家人の様子がのぞかれないように心して、最も便利な位置に設ける。
湯殿、便所は清潔を旨とする所であるので、なるべく座敷より見えない場所とする。特に便所は、庇屋づくりとする。
土蔵は本屋と離す。
縁側は交通用のみならず、雨天のときは子どもの遊び場になることもあり、東南向きに設けるのが良い。
縁側の幅は、普通3尺であるが、中等以上の住家では、4尺以上6尺ぐらいとすべきである。
以上は、間取りを考える上の留意点を、ごく簡単にまとめたものである。詳細は、図で別途詳しく説明する(⇒「下巻」)。
なお、古来、丑寅の間(俗に鬼門と称す)を忌み、窓、便所などを設けず、壁あるいは押入とする習慣がある。これは疑問がある説であるが、そのような言い伝えがあるということだけは記しておく。
〈「総論」の章終り〉
**********************************************************
間取りについての書物は、各時代に、いろいろと出ています。この書を読んで、思わず読み比べてみたくなりました。
そして、新聞の折り込み広告で見る「間取り」を見るにつけ、いったい今、住居について、学校でどのように教えられているのかも知りたくなりました。
次回は、「二 製図の準備」「三 住家を建設せんとするとき要する図面」の章を紹介します。